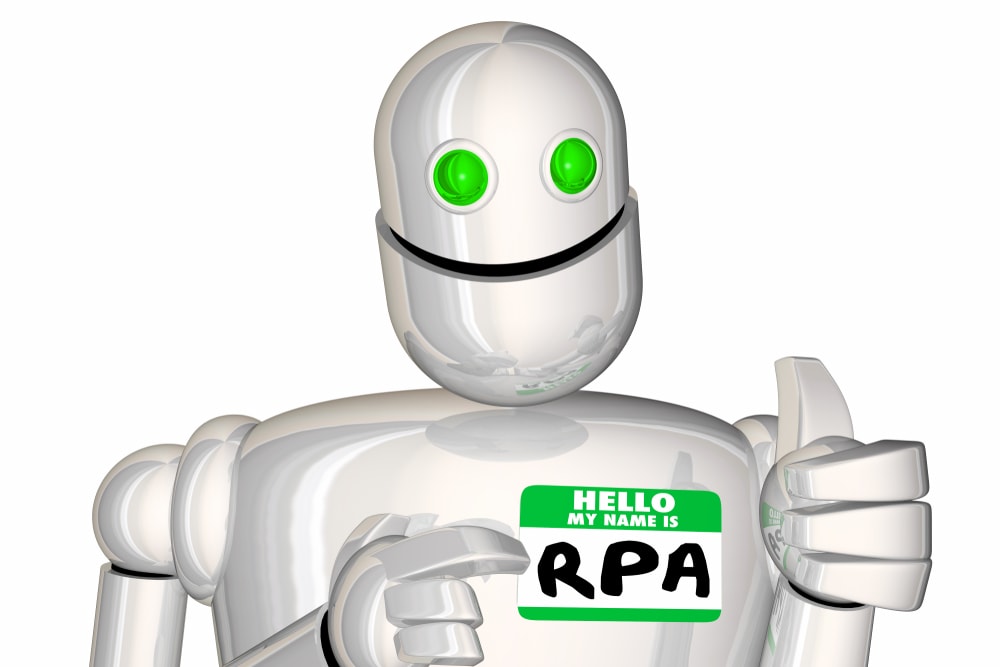
公認会計士 中田清穂の会計放談~RPA編~ 2019.12.01 (UPDATE:2020.12.21)
中田 清穂(なかた せいほ)
最近、RPAに関連するセミナーやイベントへのご依頼が増えてきました。
パネルディスカッションのモデレーターもやりました。
パネルディスカッションを開催する前には、通常「事前の打ち合わせ」をします。
私の場合、事前打ち合わせをしても、当日のやり取りやその中での思い付きで、事前打ち合わせ通りにならないことがとても多くパネラーや主催者を困らせます。
あるパネルディスカッションの事前打ち合わせで、あるパネラーの方(上場会社経理部長)から、
「弊社経理部門では、すでにRPAでロボを40~50体作って稼働していて、かなり経理業務の自動化が実現できました。そして、RPAによる自動化をさらに促進した後に経理部門での業務をどうするのかを検討するフェーズに入っています。したがって、パネルディスカッションでは、RPAの導入が成功した後で、経理業務をどうしていくのかについて、他社のパネラーのご意見を伺う形にしていただくとありがたいです。」
RPAの導入については、今や、情報収集を始めたばかりの会社も多い反面、相当程度導入が進んでいる会社も出始めていて、いわゆる「二極化」現象になっていると実感します。
RPAでの業務の自動化が進んだ後について、パネルディスカッションで出た意見は、以下のようなものでした。
実に6名のパネラーをそろえたパネルディスカッションだったのですが、パネラー全員のレベルが高く、RPAの導入も成功した企業ばかりでした。
大変貴重な内容で有益だと思います。
パネルディスカッションでのパネラーの意見で共通しているのは、誰も「費用対効果」を強調する人がいなかったということです。
言い換えれば、今回のパネラーの会社では、経理業務の自動化による「費用削減」を目的としている会社はなかったということです。
「ガバナンスの強化」とか「将来予測情報の策定」などのために、「人間でなくてもできること」はできるだけ自動化しているのです。
今できていないことで「人間でやりたい」ことは何か、それは会社によって異なるようです。
しかし、「やりたい」けど、決算業務・経理業務に忙殺されてできない、そんな状況を打破するために、RPAを利用している会社ばかりだったと言えるでしょう。
今年のこの私のコラムは「RPA特集」でした。
「RPA特集」は今回で最終回とします。
この特集の初めから、「どうすればRPAの導入が成功するか」を中心に解説してきました。また、どうして失敗するのかについても、私の経験や考えを説明してきました。
そこから感じ取られるのは、「費用対効果」を目的とするRPAプロジェクトはとん挫・失敗し、「生産性向上」と「人間の業務転換」を目的とする会社が成功しているということです。
「費用対効果」と「生産性向上」は相互に関連しますが、本質が全く異なります。
この二つを混同すると、目的が不明確になり、プロジェクトは失敗します。
RPAの話から、目的志向の重要性まで、いろいろなお話ができて良かったかなと自己評価しています。そして、RPAはまだまだ進化しています。またRPAユーザーもどんどんレベルアップして成長しています。
これからも、RPA導入の現場から目を離さないようにしようと考えています。
来年もこのコラムを、どうぞよろしくお願いいたします。
来年は、明るく楽しい経理部門になりますように!!
中田 清穂(なかた せいほ)
1985年青山監査法人入所。8年間監査部門に在籍後、PWCにて 連結会計システムの開発・導入および経理業務改革コンサルティングに従事。1997年株式会社ディーバ設立。2005年同社退社後、有限会社ナレッジネットワークにて、実務目線のコンサルティング活動をスタートし、会計基準の実務的な理解を進めるセミナーを中心に活動。 IFRS解説に定評があり、セミナー講演実績多数。