
公認会計士 中田清穂の会計放談 2021.12.09 (UPDATE:2024.11.22)
中田 清穂(なかた せいほ)
貸借対照表って何ですかね。
過去、「何をいくらで買ったか」が左側(借方)に記載されます。
過去、「どこからいくら調達したか」が右側(貸方)に記載されます。
「貸借対照表ってそれだけのこと。」
「要するに『過去の活動の記録』でしかない。」
多くの経理関係の方々はそう考えているかもしれません。

経営判断は、企業の価値を最大化すること、そのために、社内にある経営資源(人材、資産、資金)をどの事業、どの部門にいくら配分すればよいか、つまり、「経営資源の最適配分」を行うことですね。
経営資源の最適配分を行うということは、「儲かる事業を『選択』して、儲からない事業から資源を引き揚げて、儲かる事業に資源を『集中』させる」ことに他なりません。
したがって、「儲かる事業」を的確にキャッチすることが、何よりも大切です。
その際に、貸借対照表は役に立たないと考えられています。
しかし、考えてみてください。
「経営資源」を最適に配分することで、企業の価値は上がるのですから、社内にどのような「経営資源」がどのくらいあるのかを把握することは、いの一番に着手するべきです。
この場合の「経営資源」は、人材、資産及び資金ですが、そのうち資産及び資金は、貸借対照表に記載されいるのです。
しかし、「過去の活動の記録」でしかない貸借対照表に記載されている資産及び資金から、どれくらいの価値が生み出されるかは、読み取れません。
資産及び資金から、どれくらいの価値が生み出されるかを知るためには、それらの資産及び資金を「将来どう使うか」を決めておかなければなりません。
今ある資産及び資金を、既存であれ、新規であれ、ある事業に使うことを決めれば、その資産及び資金を使うことで、将来どれだけのキャッシュが得られるかを予想することができます。
これがいわゆる「使用価値」です。
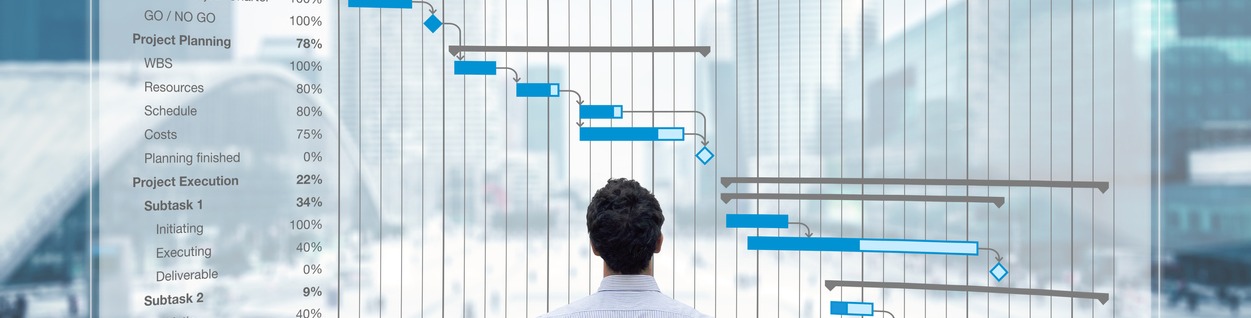
資産の「簿価」と「使用価値」を比べて、「使用価値」の方が高ければ高いほど、その資産は、企業の価値を高める資産だということになります。
これは、経営判断にとって、とても有用な情報です。
というか、この情報なくして、「選択と集中」なんて、上っ面のお題目に過ぎないでしょう。
だって、将来儲かるための資産がどれで、どのくらい儲かるかを知らずに経営をしているんですから、ずさんな経営をしていると言っても良いでしょう。
逆に「簿価」と「使用価値」を比べて、「簿価」の方か高ければ、「減損処理」の検討が必要になります。
だって、その資産から将来得られるキャッシュが、過去支払った金額よりも小さいのですから、経営判断としては、企業の価値を高める資産ではないものだということになるでしょう。
ここで重要なポイントは、経営判断に役立つ財務情報は、制度会計だけをやっていても出てこないということです。
経営判断に役立つ財務情報は、資産について、過去買った金額を記録して、あとは減価償却などを淡々とやっていればよい、という考えでは、絶対に得られない情報です。
「支出を記録して後は減価償却だけ」というのは、楽ちんです。
しかしそれでは、経営情報は作れないのです。
そもそも「経理」は「経営を管理」するためのものです。
税務申告や制度開示のための決算は義務ですからきちんとやる必要はあります。
しかし、税務申告や制度開示は、「経営を管理」するものではありません。
ここを理解できるかどうかが、経営判断に役に立つ財務情報を作れる経理になれるかどうかの分かれ道だと思います。
過去の成績表を穴が開くまで凝視しても、将来の成績は上がらないのです。
中田 清穂(なかた せいほ)
1985年青山監査法人入所。8年間監査部門に在籍後、PWCにて 連結会計システムの開発・導入および経理業務改革コンサルティングに従事。1997年株式会社ディーバ設立。2005年同社退社後、有限会社ナレッジネットワークにて、実務目線のコンサルティング活動をスタートし、会計基準の実務的な理解を進めるセミナーを中心に活動。 IFRS解説に定評があり、セミナー講演実績多数。