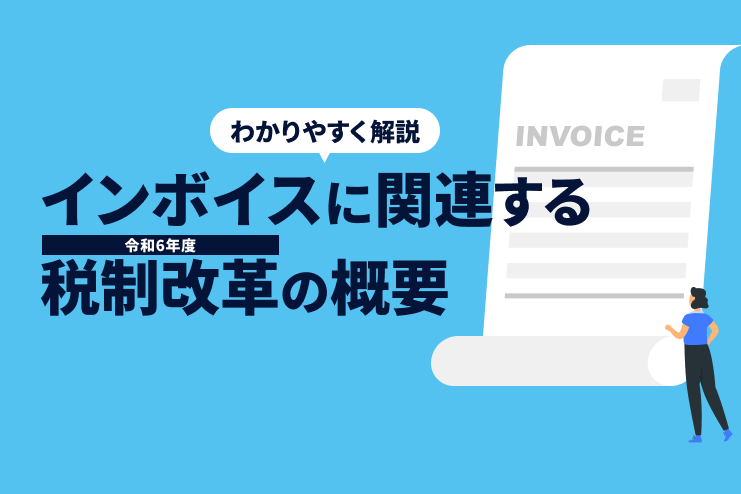
トレンド情報 2024.04.23 (UPDATE:2025.04.15)
スーパーストリーム
近年頻繁に施行されている税制改革は、企業経営において無視できない重要な変更をもたらしています。特に令和5年10月に運用が開始されたインボイス制度は、多くの企業が直面する複雑な課題です。
この改革により、消費税の適正な申告と納税が求められるため、企業を経営する方や経理を担当する方は、その理解と対応が不可欠となります。しかし、毎年のように施行される税制改革の内容を把握して、適切な対策を講じることは容易ではありません。
そこで今回は、インボイスに関連する令和6年度の税制改革の概要をわかりやすく解説します。企業の経営者の方はもちろん、経理を担当する方も、ぜひ参考にしてください。
インボイス制度とは、消費税の適正な転嫁を確保し、仕入税額控除の適用を受けるために必要な請求書(インボイス)の保存方式のことです。
この制度では、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を記載したインボイスを交付し、買手はこれを保存することで仕入税額控除を受けることができる制度です。
インボイス制度の具体的な特徴としては、以下の3つがあります。
インボイス制度は、消費税の透明性を高め、税制の公平性を保つために、令和5年10月1日から導入されました。
令和6年度の税制改革では、インボイス制度に関連していくつかの重要な変更がありました。
主な変更点は以下3つです。
それぞれ解説します。
自動販売機特例の適用取引や回収特例が適用される取引(税込3万円未満)において、帳簿への住所等の記載が不要となりました。これにより、自動販売機や自動サービス機による課税仕入れ、または使用の際に証票が回収される課税仕入れについて、より簡易な帳簿記載が可能となります。これにより、記載の手間が削減され、経理処理が簡素化されます。
帳簿への記載例は、以下の通りです。
出典:国税庁のウェブサイトより
なお、この要件は、インボイス制度が実施された令和5年10月1日以降の取引に適用されます。
国外事業者に対する簡易課税制度の適用排除が明確化され、所得税法または法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者は、簡易課税制度の適用を受けられなくなりました。これにより、国内事業者との公平性が図られます。
なお、この改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに関する経過措置が見直され、一定の条件を満たす場合に限り、経過措置の適用が認められることとなりました。具体的には、同じ取引先と同じ事業年度中に10億円を超える取引を行った場合、10億円を超えた金額については経過措置の適用がされないことになりました。
なお、この改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
上記の3つの変更は、インボイス制度の運用をより効率的かつ実務に即したものにすることを目的としています。
さらに詳しい内容ついては、国税庁のウェブサイトで公開されている資料をご参照ください。
インボイス制度に関連する税制改革は、企業経営にいくつかの重要な影響を与えることが予想されます。
主な影響としては、以下の4つが挙げられます。
企業は適格請求書を発行し、保存する義務があります。これには、適用税率や消費税額などが正確に記載された請求書の管理が含まれます。
適格請求書の発行ができない事業者は、仕入税額控除を受けることができなくなるため、経営に影響を及ぼす可能性があります。
課税事業者は適格請求書を発行する必要がありますが、免税事業者は発行できません。そこで、免税事業者が課税事業者になるためには、消費税の申告・納税の義務が発生します。これにより、小規模事業者やフリーランスの経営戦略に影響が出る可能性があります。
インボイス制度に対応するためには、既存の会計システムや業務プロセスを見直し、必要に応じて更新することが求められます。これにはコストと時間がかかるため、特に中小企業にとっては大きな負担となる可能性があります。
取引先が課税事業者か免税事業者かによって、取引条件が変わることがあります。免税事業者からの仕入れでは仕入税額控除が受けられないため、取引先選定に影響を及ぼす可能性があります。
インボイス制度の改革に伴い、経理や会計の実務を適切に行うためには、以下のようなポイントに留意する必要があります。
受け取ったインボイスが適格請求書であるかを確認し、適格請求書発行事業者として登録されている取引先からのものであることを確認する必要があります。また、インボイスには適用税率、消費税額、事業者の登録番号などが記載されている必要があるため、注意が必要です。
税区分が複雑化するため、会計システムを更新し、適切かつ自動的に税区分が選択できるようにする必要があります。また、経過措置に応じた税区分がタイムリーに切り替えられるようにシステムの対応を確認することも重要です。
仕入税額控除を受けるためには、区分経理に対応した帳簿および適格請求書等の保存が必要です。日々の記帳段階から取引を税率ごとに区分経理しておくことが求められます。
インボイスの保管が必要な取引とそうでない取引を正しく分別し、必要な証憑を適切に保管することが大切です。なお、証憑(しょうひょう)とは領収書や請求書のことを指します。
また、現⾏法では税込⽀払額が3万円未満の場合は、請求書等を保存しなくても法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいとされています。そのため、特に、税込支払額が3万円未満の証憑には、注意が必要です。
企業では、これらのポイントに注意し、インボイス制度の改革に伴う経理や会計の実務を適切に行うことが重要です。
令和6年度のインボイス制度に関連する税制改革の注意点については、以下のポイントが挙げられます。
インボイス発行事業者の登録を取り消す場合、翌課税期間の初日から起算して15日前までに届出書を提出する必要があります。登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されない点に注意が必要です。
課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日前から課税事業者となる同日を含む課税期間に、インボイス発行事業者の登録を受け、2割特例の適用を受けるケースがあります。この特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができますが、申告時に届出書を提出しても当該申告分について簡易課税制度の適用を受けることはできません。
これらのポイントに加えて、令和6年度税制改正の大綱には、自動販売機特例や回収特例が適用される取引における帳簿の記載事項の見直しなど、インボイス制度に関連するさまざまな見直しが示されています。
税制改革に関する最新情報は常に変更される可能性があるため、専門家の意見を求めるか、国税庁の公式情報を確認することをおすすめします。また、具体的なケースに応じた対応が必要になる場合があるため、事業の実態に合わせた適切な対策を講じることが重要です。
令和6年度のインボイス制度と消費税申告に関する改革の詳細については、以下のポイントを押さえることが重要です。
自動販売機特例や回収特例が適用される取引において、3万円未満のものに限り、帳簿への住所等の記載を不要とする改正が行われました。これにより、帳簿の記載が簡素化され、事業者の負担が軽減されます。
国外事業者に対しては、簡易課税制度の適用を認めないこととし、小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用も同様とされました。これにより、国内事業者との公平性が図られます。
簡易課税適用者が税抜経理方式を採用する場合の経理処理方法について、所要の見直しが行われました。これにより、仕入税額控除の計算が明確化され、事業者の適切な税務処理が支援されます。
これらの改革は、インボイス制度の運用をより効率的かつ公平にするためのものであり、事業者はこれらの変更に注意して対応することが重要です。
このように、インボイスに関連するもの以外にも、税制改革は複雑かつ頻繁に行われる傾向にあります。そこで、企業の経理や会計業務には、最新の情報が自動でアップデートされる信頼性の高いクラウド会計システムの導入がおすすめです。
クラウド会計システムがインボイス制度や税制改革への対応におすすめされる理由には、以下のような特徴があるからです。
クラウド会計システムは、常に最新の税法に対応しており、バージョンアップの手間が省けます。
クラウド会計システムは、他の業務システムと連携して業務を効率化でき、請求書の発行から帳簿の管理まで一元化できます。
クラウド会計システムは、クラウドにアクセスできる環境があればどこでも業務が進められ、リモートワークへの対応が容易です。
クラウド会計システムは、電子帳簿保存法にも対応しており、紙の削減による環境保護への対策や業務効率の向上に期待できます。
これらのメリットにより、インボイス制度や税制改革への対応がスムーズになり、事業者の負担が軽減されるため、クラウド会計システムの導入が推奨されています。
そこでおすすめしたいのが、キヤノンITソリューションズの「SuperStream-NX」です。
「SuperStream-NX」は、クラウド会計システムとして多くの企業に選ばれています。
高度な機能と操作性を備え、コスト削減や保守・管理業務の負担軽減が可能です。さらに、高いセキュリティと可用性を提供し、ビジネスの成長に応じた柔軟な拡張性も魅力です。
AI-OCRを活用した業務の自動化と効率化も実現しており、手作業によるミスを減少させ、業務効率を大幅に向上させることが可能です。
これらの理由から、「SuperStream-NX」は非常に優れた選択肢となります。
そこで、まずはオンラインでお気軽に資料請求してみてください。
また、自社に必要なシステムの種類や選び方がわからない場合は、いつでもキヤノンITソリューションズにご相談ください。貴社に適したソリューションを提供いたします。
国内1万社以上が導入する「SuperStream-NX」。下記の動画では、クラウド活用、システム連携、法改正対応の3つのポイントを解説しています。ぜひご視聴ください。