
公認会計士 中田清穂のIFRS徹底解説
中田 清穂(なかた せいほ)
親会社が連結財務諸表についてIFRSを適用することになると、重要な子会社には、IFRSベースの財務諸表を作成するよう、親会社から要請される場合があります。
本コラム『子会社のIFRS』では、親会社からIFRS対応をせまられた子会社の実務に役立つと考えられるテーマをとりあげたいと思います。
今回は、子会社にとって理解しにくい「開始仕訳」あるいは「繰越仕訳」と表現される仕訳について解説したいと思います。
子会社がIFRSベースの財務諸表を作成するパターンには、大きく分けて2つのパターンがあります。
(1)パターン1下図のように、会計システムで「複数元帳対応」を行い、一つひとつの取引について、日本基準とIFRSの両方の帳簿に仕訳を入力するパターンです。
この場合、複数の元帳から、日本基準の財務諸表とIFRSの財務諸表が、それぞれ作成できます。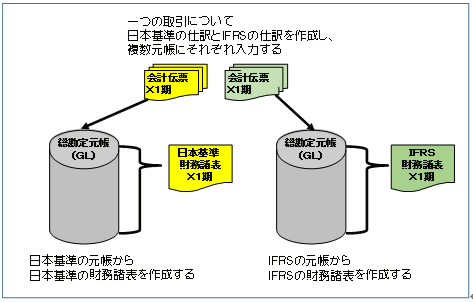
下図のように、会計システムでは、日本基準にのみ対応して、一つひとつの取引の仕訳は、日本基準の元帳にのみ入力します。
この場合、まず日本基準の元帳から、日本基準の財務諸表が作成されます。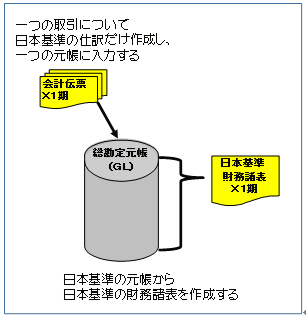
そして、日本基準とは異なる処理が要求される論点(会計基準差異項目)について、「組替仕訳」を作成し、日本基準の財務諸表に「組替仕訳」を加味して、IFRSの財務諸表を作成します。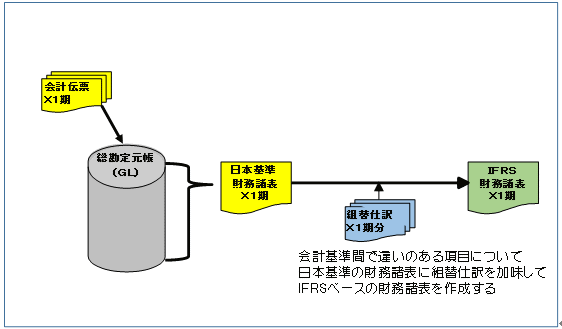
会計システムでの「複数元帳対応」をするには、コストや時間がかかるために、パターン2で対応されるケースが多いようです。
また、数年後にはパターン1の「複数元帳対応」を目指すが、当面は、パターン2でしのごうとするケースも多いようです。
いずれにしても、パターン2では、子会社にとって聞きなれない「組替仕訳」を作成する必要があります。
(1)会計システムの繰越処理
新しい年度になると、ほとんど例外なく、会計システムの「残高繰越処理」が行われます。
年度末の残高データを、新年度の期首残高データとして、会計システムにセットする処理です。
この「残高繰越処理」を実行することで、新年度の仕訳が入力できるようになります。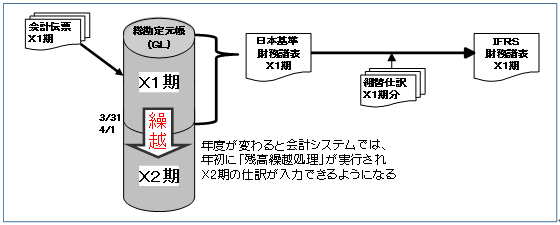
「残高繰越処理」の実行後、新年度の一つひとつの取引の仕訳は、日本基準の元帳にのみ入力していきます。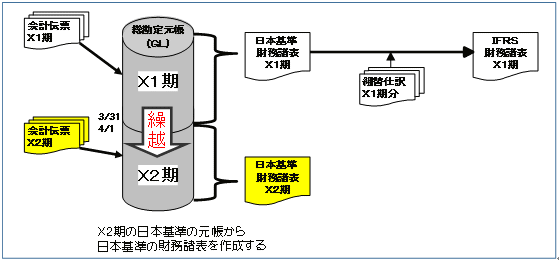
IFRSの財務諸表は、前期の財務諸表に対して「繰越処理」を行って作成するわけにはいきません。
パターン2では、IFRSを作成する元帳がないからです。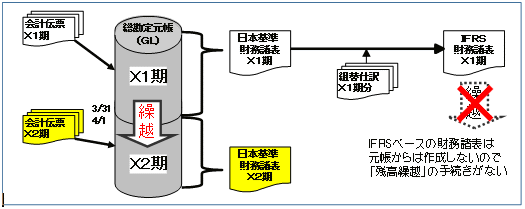
そこで、新年度の日本基準の財務諸表に、新年度の仕訳に係る会計基準差異の組替仕訳を加味する前に、前年度作成した組替仕訳について「繰越処理」を行うのです。
これを図で表すと以下のようになります。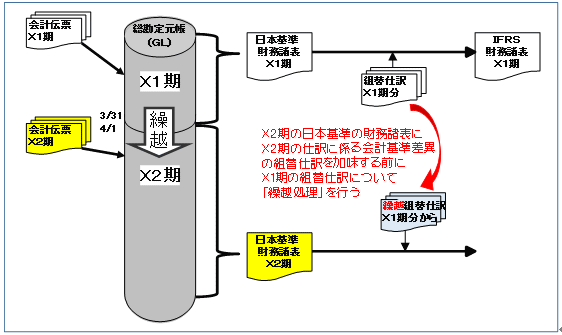
日本基準の元帳がある会計システムでの「残高繰越処理」実行後、当期の仕訳を加味した日本基準の財務諸表①に、前年度の組替仕訳から作成した繰越組替仕訳②と、当期発生した日本基準の仕訳に対する当期組替仕訳③を加味してIFRSベースの財務諸表を作成します。
(下図参照)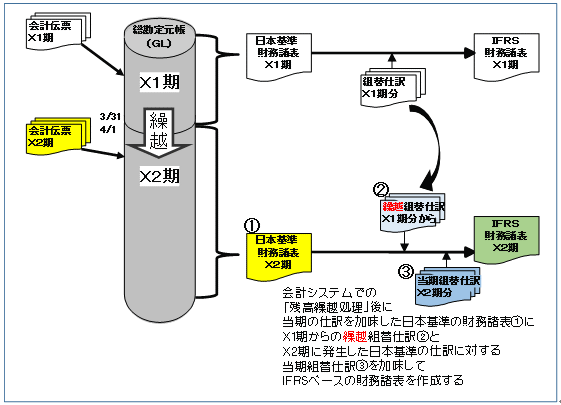
中田 清穂(なかた せいほ)
1985年青山監査法人入所。8年間監査部門に在籍後、PWCにて 連結会計システムの開発・導入および経理業務改革コンサルティングに従事。1997年株式会社ディーバ設立。2005年同社退社後、有限会社ナレッジネットワークにて、実務目線のコンサルティング活動をスタートし、会計基準の実務的な理解を進めるセミナーを中心に活動。 IFRS解説に定評があり、セミナー講演実績多数。