
公認会計士 中田清穂の実は深いSDGsと経理の関係徹底解説 2022.04.28 (UPDATE:2024.11.21)
中田 清穂(なかた せいほ)
前回のコラムでは、GPIFなどの投資家が投資の判断をする場合に、いわゆる「財務情報」だけでなく、「ESGへの対応」などの「非財務情報」も投資判断の材料にしてきているというお話をしました。
それでは、最近の日本の上場企業が、SDGsやESGをどのくらい開示しているのでしょうか。
(1)PwCレポートの調査概要
このレポートは、以下のような内容で、日本におけるSDGsとESGの開示状況を調査しています。
① 調査対象と調査のやり方
PwCレポートでは、「テキストマイニング」という手法を使って調査が行われました。
具体的には、有価証券報告書の以下の記載箇所を対象にして、「SDGs」や「ESG」といった単語が使われている企業を、ITのしくみを使って抽出したのです。
i. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
ii. 事業等のリスク
iii. コーポレート・ガバナンスの状況等
② 調査期間
2017年3月31日に終了する事業年度から4年間です。
③ 対象企業の概要
調査対象となった企業の売上規模は以下です。
i. 1,000億円未満:766社
ii. 1,000億円以上5,000億円未満:468社
iii. 5,000億円以上:236社
(2)SDGsの開示状況
上記1(1)①で示した、有価証券報告書の3か所の記載箇所で、「SDGs」という単語を使用している企業の状況が以下の図です。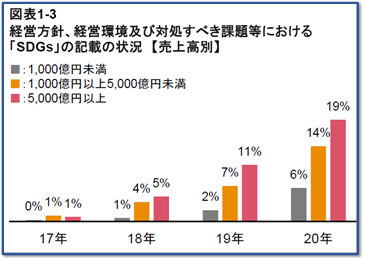
この図でわかることは、4年前にはほとんど開示していなかった状況から、4年間で開示する企業が増えていることは明らかです。
また、売上規模が大きな会社ほど、開示する割合が大きいと言えます。
ただ、売上規模が、5,000億円以上の大企業でも、まだ19%にとどまっているとも言えます。
すなわち、「SDGsを開示する企業は増加傾向にあるが、まだまだ十分に広がっているとは言えない」と言えるでしょう。
(3)ESGの開示状況
次に、上記1(1)①で示した、有価証券報告書の3か所の記載箇所で、「ESG」という単語を使用している企業の状況を見てみましょう。以下がその状況を表した図です。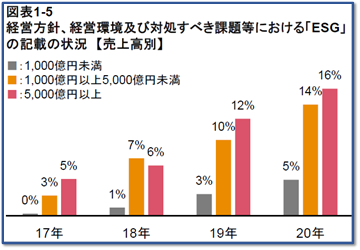
この図でわかることは、「SDGs」の開示と比較すると、4年前にも数パーセントの開示がされていて、やはり4年間で開示する企業が増えています。
また、売上規模が大きな会社ほど、開示する割合が大きいのは、「SDGs」と同じ傾向です。
さらに、売上規模が、5,000億円以上の大企業でも、まだ16%にとどまっているとも言えるのも「SDGs」と同じ傾向です。
したがって、「ESGを開示する企業は増加傾向にあるが、まだまだ十分に広がっているとは言えない」と言えるでしょう。
前回のコラムで、ESGの開示が、投資家の意思決定とかかわりがあることをお話しました。
したがってESGは数年前から一定数の企業が開示していたのだと考えられます。
しかし、PwCレポートの実証データに基づいて、「ESG」と「SDGs」の開示状況を比較すると、「ESG」の増加の仕方は「SDGs」増加の仕方よりも緩やかになっています。
これは、上場企業では、「ESG」よりも「SDGs」の開示の方が、より積極的になっていると言えるでしょう。
自社の株価との関連性が強いと感じられるESGよりも、SDGsの開示が積極的になっているのはなぜでしょうか。
それは、投資家の関心が、ESGよりもSDGsの方にシフトしているからではないかと、私は考えています。
特にSDGsの17の目標の中でも「気候変動への対策」が、最近クローズアップされてきていることと関係があるように思います。
その根拠が、「気候変動に関する国際的な開示基準」をめぐる最近の動きです。
次回は、「気候変動に関する国際的な開示基準」をめぐる最近の動きについてお話しようと思います。
中田 清穂(なかた せいほ)
1985年青山監査法人入所。8年間監査部門に在籍後、PWCにて 連結会計システムの開発・導入および経理業務改革コンサルティングに従事。1997年株式会社ディーバ設立。2005年同社退社後、有限会社ナレッジネットワークにて、実務目線のコンサルティング活動をスタートし、会計基準の実務的な理解を進めるセミナーを中心に活動。 IFRS解説に定評があり、セミナー講演実績多数。