
トレンド情報 2025.04.13 (UPDATE:2025.04.13)
スーパーストリーム
企業会計には「財務会計」と「管理会計」という2つの重要な分野があり、それぞれ役割や目的が異なります。
財務会計は外部の利害関係者への報告を目的とし、管理会計は経営判断のための内部資料として活用されます。
これらを正しく理解することは、企業運営における意思決定や効率的な管理を可能にする重要な要素です。
そこで今回は、財務会計と管理会計の違いについて、企業会計の基礎知識と目的や役割とともに詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
まずはじめに、財務会計と管理会計の定義と役割の違いを比較します。
|
項目 |
財務会計 |
管理会計 |
|
定義 |
企業の財務状況を外部の利害関係者に報告するための会計 |
経営者や管理者が意思決定を行うための内部向け会計 |
|
目的 |
企業の財政状態と経営成績を外部に開示・報告すること |
経営管理に役立つ情報を提供し、意思決定を支援すること |
|
報告対象 |
株主、投資家、債権者、税務署など外部の利害関係者 |
経営者、各部門のマネージャーなど内部の意思決定者 |
|
法的規制 |
会社法、金融商品取引法などに基づく法定開示が必要 |
法的規制なし、企業が任意で導入・運用 |
|
報告書類 |
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書など |
部門別収益性分析、原価計算、予算管理資料など |
|
情報の性質 |
過去の実績に基づく客観的な情報 |
将来の計画や予測を含む戦略的な情報 |
|
作成頻度 |
年次、四半期など法定で定められた期間 |
必要に応じて随時(月次、週次など) |
以下で、主な違いを詳しく解説します。
財務会計は、企業外部の利害関係者(投資家、債権者、税務署など)に対して、企業の財務状況を報告するのが目的です。財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書など)を通じて、企業の財政状態と経営成績を開示し、外部からの評価や投資判断、融資決定の材料を提供します。
一方、管理会計は、経営者や管理責任のある従業員が企業をマネジメントするための内部向けの会計です。経営管理に役立つ情報を提供し、意思決定を支援するのが目的です。管理会計では、未来の計画や予算の見積もり、経営戦略の立案支援など、より柔軟で戦略的な情報を扱います。
財務会計は、法律や会計基準に基づいて行われるものです。企業には、会社法や税法、金融商品取引法などの法律に従って、正確性と透明性を重視した財務諸表を作成し、外部に公表する義務があります。このため、財務会計の運用には厳格な規則があり、自由度は限られています。
一方、管理会計には法律による規制がなく、企業が任意で導入・運用できるのが特徴です。そのため、各企業の経営目標や重要指標に応じて、柔軟に会計システムを設計できます。この自由度の高さにより、企業は自社の経営に最適な管理会計システムを構築し、効果的な意思決定や業績管理を行うことが可能です。
財務会計の主な報告対象者は、株主、投資家、債権者、税務署など、外部の利害関係者(ステークホルダー)です。
適切な財務諸表は、これらのステークホルダーに対して、企業の財務状況や業績を明確に伝えるための重要な書類です。財務諸表を通じて企業の資産、負債、資本金、収益、利益などの情報を提供することで、ステークホルダーは投資判断や融資決定を行います。
一方、管理会計の報告対象者は、経営者や各部門のマネージャーなど、企業内部の意思決定者です。経営陣に対して、より詳細で戦略的な情報を提供することで、経営目標の達成や経営課題の解決をサポートします。
そこで、部門別の収益性分析、原価計算、予算管理など、内部管理に必要な情報を柔軟に作成・報告するのです。
下記の資料では、会社の経営状況を表す財務諸表のうち、売上・利益等の業績を明らかにする損益計算書について、わかりやすく解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。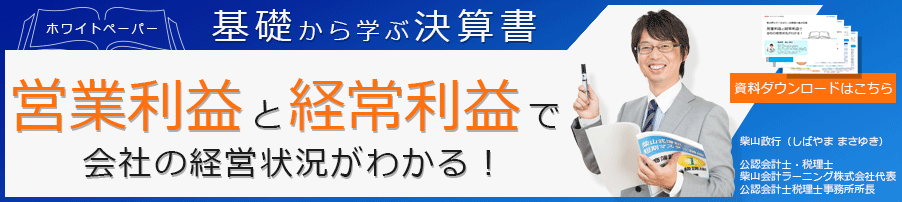
次に、企業会計の2大体系(財務会計と管理会計)を比較して分析します。
財務会計は、主に財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書など)の作成が目的です。これらの財務諸表は、外部の利害関係者に企業の財政状態と経営成績を報告するために作成され、法律や会計基準に基づいて統一された形式で作成されます。
一方、管理会計は、経営分析資料の作成が主な機能です。これには、部門別収益性分析、原価計算、予算管理資料などが含まれます。管理会計の資料は、経営者や各部門のマネージャーが意思決定を行うために使用され、企業の内部ニーズに合わせて柔軟に設計されるのが特徴です。
財務会計では、主に過去のデータを処理し、報告することに焦点が当てられます。財務諸表は、特定の期間(通常は年次または四半期)の企業活動の結果を示すものです。
これに対し、管理会計は過去のデータを分析するだけでなく、将来の計画や予測にも重点を置いているのが特徴です。例えば、損益分岐点分析を用いて将来の売上目標や経費圧縮の計画を立てたり、予算管理を通じて将来の業績を予測したりします。また、管理会計では10年間の財務諸表の数値を分析することで、経営の転換時期を知ることができるなど、より長期的な視点での分析も行います。
財務会計は主に金額単位で情報を記録し、報告するのが特徴です。そのため、財務諸表には、資産、負債、資本、収益、費用などが貨幣価値で表示されます。
一方、管理会計では、より多様な指標が活用されるのが特徴です。金額単位の情報に加え、非財務指標も重要視されます。例えば、生産性を測る指標、顧客満足度、従業員の定着率などです。また、管理会計では財務諸表の比率分析を行い、収益性、生産性、安全性、成長性などの観点から、企業の状態を多角的に分析します。このように、管理会計に金額以外の指標を併用することで、より包括的な経営分析と意思決定の支援を行います。
下記の資料では、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」について、公認会計士がわかりやすく解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。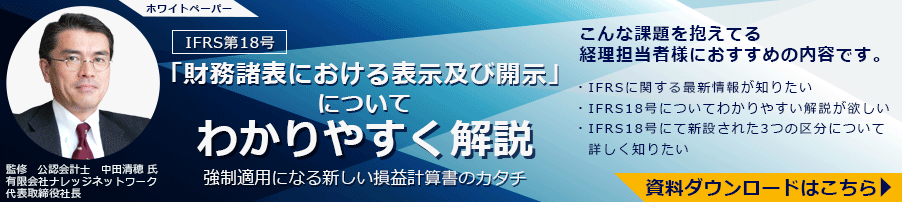
以下では、管理会計の主要なツールと、その活用方法を解説します。
損益分岐点の分析は、企業が利益を出し始める売上高を特定するための重要なツールです。最小二乗法を用いて、売上高と総費用のデータから固定費と変動費を分離し、損益分岐点を計算できます。
この分析により、企業は売上高が何%減少すれば赤字になるかを把握できます。例えば、ある企業では、売上高が半減しない限り赤字にならないことが分かりました。
この情報は、経営戦略の立案や、リスク管理に活用できます。また、決定係数(R²)を確認することで、分析結果の信頼性も評価できます。
限界利益は、経営判断に不可欠な指標です。売上高から変動費を差し引いて計算され、固定費を賄った後の利益を示します。
限界利益は、事業の存続判断、価格設定、利益計画立案などに活用される重要な指標です。例えば、ある部門が赤字でも、限界利益がプラスであれば、その部門を存続させることで会社全体の利益に貢献する可能性があります。
また、価格設定においても、限界利益を基準にすることで、適切な値下げ幅を決定できます。
このように、経営者が限界利益を理解して活用することで、より正確な経営判断が可能となり、企業の競争力を高めることが可能です。
予算管理と業績評価を連動させるシステムは、企業の戦略実行と目標達成を支援する重要なツールです。このシステムでは、まず詳細な予算を立て、それを基準として実際の業績を評価します。
管理会計システムの分析・レポート機能を活用することで、予算と実績の差異を容易に可視化し、トレンドや異常値を迅速に把握できます。また、シミュレーション機能を用いて、様々な状況下での業績予測を行うことも可能です。
これにより、経営者は迅速かつ的確な意思決定を行え、必要に応じて戦略の修正や資源の再配分を実施できます。
このシステムは、組織全体の目標達成に向けた取り組みを促進し、継続的な業績改善を支援する重要なツールです。
下記の資料では、多岐に渡る業務のなかで常にスピード感と質の両軸が求められている経理・財務部門の主な「11の課題」について、どのような対応が必要かを分かりやすく解説します。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。
次に、財務会計の必須要素と法律要件について解説します。
財務会計では、企業会計原則に基づき、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を作成します。これらは、企業の財政状態や経営成績を正確かつ公正に示すことを目的とし、外部の利害関係者に対して信頼性の高い情報を提供するために重要です。
企業会計原則には「真実性の原則」や「明瞭性の原則」など7つの基本原則があり、これらに従うことで透明性と比較可能性が確保されます。特に上場企業では、金融商品取引法に基づき、有価証券報告書として財務諸表を開示する義務があります。
関連記事:企業会計原則とは?公正な会計処理を行うための基本ルール7つを解説
財務会計と税務申告は、相互に密接に関連するものです。法人税法では、課税所得を計算するために財務諸表が基礎資料として使用されます。ただし、会計上の利益と税務上の所得は異なる場合があるため、減価償却費や引当金などで調整が必要です。このため、税効果会計を活用して一時差異を管理し、税負担を適切に報告します。
また、法人税申告書の作成では、財務諸表だけでなく、その注記や補足資料も重要な役割を果たします。さらに、電子帳簿保存法への対応も進めることが、税務調査への準備を整えるために重要です。
四半期報告(四半期決算)は、金融商品取引法に基づき上場企業が四半期ごとに作成するもので、主に投資家に短期間での業績動向を提供することが目的です。
一方、年次報告(有価証券報告書)は事業年度全体の経営状況を包括的に示すもので、より詳細な情報が求められます。四半期報告では簡略化された形式での連結財務諸表が中心となるため、一部項目(キャッシュフロー計算書など)が省略される場合も少なくありません。これに対し、有価証券報告書では個別財務諸表も含めた詳細な開示が行われます。
ビジネスの進化において、会計システムのリプレイスは決して軽視できない重要な決断です。そこで下記の資料では、経理・財務部門と情報システム部門の方たちに向けて、リプレイス時に組織全体を見直す戦略的アプローチを提案しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。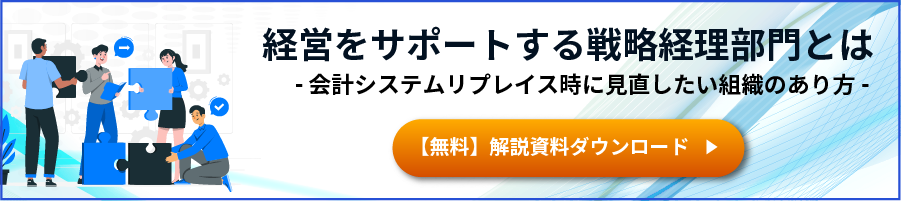
以下では、企業会計にクラウドシステムを活用するメリットと、その選び方を紹介します。
クラウド会計システムは、リアルタイムでのデータ連携を実現します。これにより、経営者はいつでもどこでも最新の財務状況を把握できるのがメリットです。
銀行口座やクレジットカードとの自動連携により、取引データがリアルタイムで反映され、常に最新の経営状態を確認できます。また、複数の拠点や部門間でのデータ共有が容易になり、迅速な意思決定や経営戦略の立案が可能です。
リアルタイムなデータの連携は、特に急激な市場変化への対応や、機会損失の回避に有効です。
クラウド会計システムの自動仕訳機能は、経理業務の効率化に大きく貢献します。なぜなら、取引データを自動で適切な勘定科目に振り分けることで、手作業による入力ミスを削減し、作業時間を大幅に短縮できるからです。
また、AIによる学習機能により、仕訳の精度が向上し、より正確な会計処理が可能となります。さらに、自動エラーチェック機能により、不整合や異常値を即座に検出し、修正することが可能です。
これにより、決算作業の効率化と、財務データの信頼性の向上を一度に実現できます。
クラウド会計システムを選定する際は、機能一覧、操作性、費用対効果を主な基準として比較検討するのがおすすめです。基本的な帳簿管理、請求書作成、経費精算機能に加え、インボイス対応など最新の法規制に対応しているかを確認しましょう。
また、使いやすいUI/UXが業務効率化に直結するため、操作性も重要な選定基準となります。費用面では、初期費用だけでなく、月額料金や追加機能のコストも含めた長期的な費用対効果を考慮することが重要です。
さらに、自社の業務規模や将来の成長計画に合わせて、スケーラビリティの高いソフトを選ぶことをおすすめします。
下記の資料では、経理・財務部門が日常利用する会計システムの刷新タイミングと、刷新時のステップとポイントを押さえつつ、「SuperStream-NX」を活用した際のメリットを具体的に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。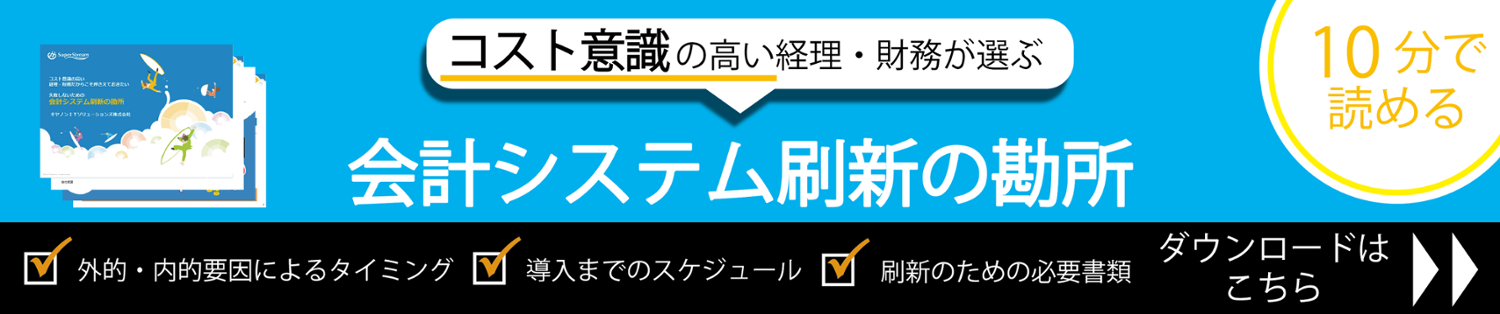
次に、統合型会計システムのメリットと導入すべき企業の特徴をそれぞれ解説します。
統合型会計システムは、企業のさまざまな業務プロセスを一元管理し、自動化することで効率化を実現します。
例えば、リアルタイムなデータ連携により、最新の財務状況をいつでも把握でき、迅速な意思決定が可能です。また、手作業の削減によりヒューマンエラーが減少し、業務の精度が向上します。さらに、データの統合管理によって部門間のコミュニケーションが円滑になり、経営資源の最適化が図れます。
これらの特徴により、企業の生産性が向上するだけでなく、コストの削減も同時に実現可能です。
統合型会計システムは、複数の部門や拠点を持つ中規模以上の企業、急成長中の企業、グループ経営を行う大手企業に特に適しているツールです。
業務プロセスの標準化や効率化が必要な企業、リアルタイムでの経営状況の把握を求める経営者、データ分析に基づく戦略的意思決定を重視する企業にとって有効です。また、コスト削減や生産性向上を目指す企業、グローバル展開を視野に入れている企業にも導入のメリットが大きいでしょう。
このように、業界を問わず、経営の効率化と競争力強化を目指す企業に適しています。
下記の資料では、累計10,345社以上が導入している「経理部・人事部ファースト」の思想に基づいて開発された、圧倒的な使いやすさを実現している「SuperStream-NX Cloud」について解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。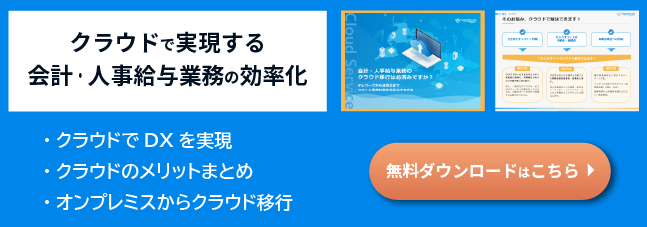
最後に、クラウド会計システムで経理業務の効率化に成功した事例を紹介します。
キヤノン電子株式会社では、統合型クラウド会計システム「SuperStream-NX」を導入したことで、経理業務の効率化に成功しました。
主な成果として以下が挙げられます。
現在は、経理部門および各事業部の経理担当者を含めた約70名がSuperStream-NXを利用。財務会計・管理会計のGL、固定資産のFA、債権管理のAR、支払管理のAP、建設仮勘定のCPなどのモジュールを活用し、外部システムとの連携にはConnectを使用しています。
製造業で原価管理システムを構築することにより、以下のような効果が期待できます。
原料、仕掛品、製品の3階層での在庫管理が可能になり、各工程での原価を正確に把握できます。
手入力項目を減らし、計算式により原価を自動計算することで、担当者ごとの見積差異を最小限に抑えられます。
生産管理システムとの連携により、見積データの転送や大日程スケジュールの自動作成が可能となり、入力作業の負荷が軽減されます。
実際原価と想定原価(原価目標)の差異分析をリアルタイムで行うことができ、生産現場のコストダウン施策に活用できます。
個別原価計算や総合原価計算など、企業の生産形態に合わせた原価計算方式を適用できます。
これらの機能により、製造業の原価管理業務が大幅に効率化され、より戦略的な経営判断が可能となります。
下記の資料では、製造業の経理業務担当者や、情報システム部門が抱える課題とその解決策を事例とともに解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。
「SuperStream-NX Cloud」は、経理部門のリモートワーク化を実現するために、以下のような機能を提供しています。
これらの機能により、在宅勤務でも効率的な経理業務の遂行が可能となり、テレワークの推進に貢献しています。
下記の資料では、卸売・小売業の経理業務担当者や、情報システム部門が抱える課題とその解決策を事例とともに解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。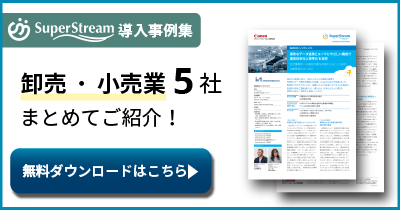
キヤノンITソリューションズの「SuperStream-NX」は、次のような特徴から、財務管理と管理会計におすすめのシステムです。
上記の特徴により、SuperStream-NXは企業のバックオフィス業務の効率化と経営戦略の支援を実現する総合的なソリューションとなっています。
下記のページでは、「経営基盤ソリューション SuperStream-NX」の詳しい内容を解説しています。登録なしでご覧いただけますので、この機会にぜひご参照ください。
経理業務のDXを進めたいとお考えの方は、オンラインでお気軽に資料請求してみてください。
また、自社に必要なシステムの種類や選び方がわからない場合は、いつでもキヤノンITソリューションズにご相談ください。貴社に適したソリューションを提供いたします。
下記の動画では、国内1万社以上が導入する「SuperStream-NX」の、クラウド活用、システム連携、法改正対応の3つのポイントを解説していますので、ぜひご視聴ください。