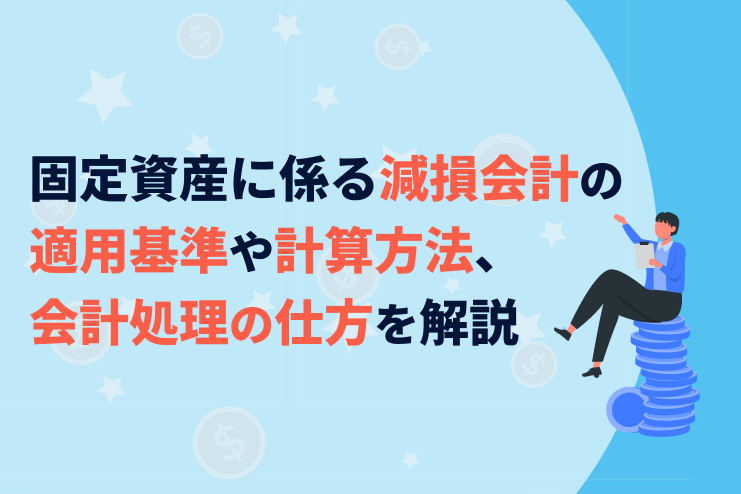
トレンド情報 2024.03.20 (UPDATE:2025.03.15)
スーパーストリーム
固定資産とは、企業が長期的に使用する土地や建物、機械装置などの資産のことです。これらの資産は、市場環境や技術革新などの影響で価値が低下することがあります。その場合、帳簿価額を実態に合わせて減額する会計処理が必要になります。これを減損会計と呼びます。
減損会計は、正しく企業の経営状況を反映するために重要な会計処理です。しかし、減損会計には、対象となる資産のグルーピングや回収可能価額の算定など、複雑な手順があります。減損会計の適用基準や計算方法、会計処理の仕方を知らないと、正確な減損損失の計上ができません。
そこで今回は、固定資産に係る減損会計の適用基準や計算方法、会計処理の仕方を解説します。ぜひ参考にしてください。
減損会計とは、資産の価値が低下した場合に、帳簿価額を回収可能な金額まで減額する会計処理です。
減損処理が必要になる理由は、財務諸表の信頼性を保つためです。
財務諸表は、企業の経営状況や財務状況を正確に反映することが求められます。しかし、固定資産の価値は、市場環境や技術革新などの要因によって変動する可能性があるため、固定資産の価値が帳簿価額よりも低下している場合には、その差額を損失として計上する必要があります。これが、減損処理です。
減損処理を行うことで、固定資産の実質的な価値と帳簿価額の乖離を防ぎ、財務諸表の信頼性を高めることができます。また、減損処理を行うことで、将来の減価償却費を減らし、利益を改善する効果も期待できます。
このように、減損会計は、財務諸表に企業の実態を正確に反映するために重要です。
減損会計の適用基準は、上場企業や大規模な会社には義務付けられていますが、中小企業は対象外です。
上場企業や大規模な会社は「固定資産の減損に係る会計基準」に従って減損会計を行います。なお、中小企業は「中小会計指針」に従って減損会計を行うことができます。
減損会計の対象資産は、主に固定資産です。
固定資産は、有形固定資産(土地、建物、機械装置など)、無形固定資産(のれん、商標、ソフトウェアなど)、投資その他の資産(投資用不動産、関連会社への出資など)に分類されます。
ただし、金融資産や繰延税金資産など、他の基準に減損処理に関する定めがある資産は、減損会計の対象外となるため、注意が必要です。
減損会計の手順は、以下のようになります。
それぞれの意味は、次のようになります。
資産のグルーピングでは、一体となってキャッシュフローを生む資産の範囲を特定します。
次に、グルーピングした資産について、減損が生じている可能性を示す事象がないか検討します。
なお、資産のグルーピングと減損の兆候については、後述します。
減損の兆候がある資産について、割引前将来キャッシュフローと帳簿価額を比較し、減損処理の必要性を判断します。
なお、割引前将来キャッシュフローの意味や算出方法については、後述します。
減損損失を認識した資産について、回収可能額と帳簿価額の差額を減損損失として計算します。
測定した減損損失を固定資産の帳簿価額から減額し、損益計算書に特別損失として計上します。
なお、減損損失の測定と会計処理の詳しい内容は、後述します。
資産のグルーピングとは、減損会計の手続きにおいて、複数の資産が一体となって独立したキャッシュフローを生み出す場合に、その範囲を特定することです。
資産のグルーピングは、他の資産または資産グループのキャッシュフローからおおむね独立したキャッシュフローを生み出す最小単位で行われます。
減損の兆候とは、資産または資産グループに減損が生じている可能性を示す事象のことです。
減損の兆候には、以下のようなものがあります。
減損の兆候がある資産または資産グループについては、割引前将来キャッシュフローと帳簿価額を比較して、減損損失の認識の判定を行います。
割引前将来キャッシュフローが帳簿価額を下回る場合に、減損損失を認識します。
減損とは、固定資産の収益性が低下したことによって、投資額の回収が見込めなくなった状態をいいます。
減損の要否の判定は、まず減損の兆候があるかどうかを判断します。減損の兆候とは、資産または資産グループに減損が生じている可能性を示す事象のことです。例えば、資産の市場価格の大幅な下落や、資産の使用範囲や方法の変更、経営環境の悪化などが減損の兆候となります。
次に、減損の兆候がある資産について、その資産が生み出す割引前将来キャッシュフローの総額が、その資産の帳簿価額を下回るかどうかを判断します。
割引前将来キャッシュフローとは、資産の使用や処分によって生じると見込まれる未来のキャッシュインフローからキャッシュアウトフローを差し引いた金額のことです。
割引前将来キャッシュフローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損の存在が相当程度に確実であるとして、減損損失を認識することになります。
回収可能価額の算定方法は、以下の通りです。
回収可能価額とは、資産または資産グループの回収可能な金額のことで、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額です。
正味売却価額とは、資産または資産グループの時価から処分費用見込額を差し引いて計算する金額です。時価とは、資産または資産グループを売却することができる市場での取引価格のことを指します。処分費用見込額とは、資産または資産グループを売却するために必要な費用のことです。
使用価値とは、資産または資産グループの継続的な使用と使用後の処分によって、生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値のことです。現在価値とは、将来のキャッシュ・フローを現在の価値に換算することで、貨幣の時間価値を考慮した金額を指します。現在価値を求める際には、割引率という指標を用います。割引率とは、将来のキャッシュ・フローを現在価値に換算する際に用いる利率のことで、資産または資産グループのリスクや期間などを反映したものです。
減損損失の測定は、減損損失を認識すべきであると判定された資産または資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、その差額を算出することです。
回収可能価額とは、資産または資産グループの売却によって得られる金額(正味売却価額)と、使用によって得られる金額(使用価値)のうち、高い方の金額です。
使用価値は、将来のキャッシュフローを現在価値に換算することで求めます。
減損損失の測定ができたら、減損損失の会計処理を行います。減損損失の会計処理は、減損損失の金額を特別損失として損益計算書に計上し、資産の帳簿価額を減額することです。
減額する方法は、直接控除方式と間接控除方式の2つがあります。
直接控除方式は、減損損失の金額を資産の取得原価から直接控除する方法です。一方、間接控除方式は、減損損失の金額を減損損失累計額という勘定科目に計上し、資産の帳簿価額を減損損失累計額で減額する方法です。
共用資産とは、複数の資産または資産グループにまたがって将来キャッシュフローの生成に寄与する資産のことです。例えば、本社の建物や研究開発部門の設備などが共用資産となります。
のれんとは、事業の買収などによって発生する、将来の収益力の見込みに基づく超過額のことです。例えば、事業の買収価額が買収した資産の時価を上回る場合、その差額がのれんとして認識されます。
共用資産とのれんの減損会計の共通点は、減損の判定と測定を、それぞれの資産単体ではなく、より大きな単位で行うことです。この場合、減損の兆候は、その大きな単位に対して判断します。
共用資産とのれんの減損会計の相違点は、減損の判定と測定を行う大きな単位の範囲が異なることです。共用資産の場合は、共用資産を含むより大きな単位で行います。のれんの場合は、のれんが関連する複数の資産グループにのれんを加えた、より大きな単位で行います。
次に、減損処理後の会計処理と開示の仕方について解説します。
減損処理を行った資産については、減損損失を控除した帳簿価額に基づいて減価償却を行います。
減損損失は、特別損失として損益計算書に計上します。
減損処理を行った資産の貸借対照表における表示は、原則として、減損処理前の取得原価から減損損失を直接控除する方法(直接控除方式)を採用するのが一般的です。ただし、減価償却を行う有形固定資産については、減損損失累計額を減価償却累計額に合算する方法(合算間接控除方式)や、減損損失累計額を独立して表示する方法(独立間接控除方式)も認められます。
重要な減損損失を認識した場合には、損益計算書に係る注記事項として、減損損失を認識した資産または資産グループの概要、減損損失の認識に至った経緯、減損損失の金額の内訳、回収可能価額の算定方法などを注記します。
また、減損会計基準を初めて適用した事業年度においては、減損損失を計上していなくとも、資産のグルーピングの方針などを注記することができます。
減損会計の事例としては、以下のようなものがあります。
不動産賃貸物件は、賃貸収入を安定的に獲得している場合、減損の兆候に該当しないと判断されることが多いですが、鑑定評価額や市場価格が著しく下落している場合、減損の兆候に該当する可能性があります。
不動産賃貸物件の回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額ですが、正味売却価額は、鑑定評価額や市場価格を参考にすると良いでしょう。使用価値は、将来の賃貸収入や処分収入を現在価値に換算することで求めることが可能です。
不動産賃貸物件の減損処理を行った場合、減損損失は特別損失として計上し、資産の帳簿価額を減額します。減額する方法には、前述した直接控除方式と間接控除方式の2つがあります。
製造業では、設備の老朽化や需要の減少などにより、減損の兆候が生じることがあります。
製造業の回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額ですが、正味売却価額は、設備の時価から処分費用見込額を差し引いて計算する金額です。使用価値は、設備の使用によって生じると見込まれる将来キャッシュフローを現在価値に換算することで求めます。
製造業の減損処理を行った場合、減損損失は特別損失として計上し、資産の帳簿価額を減額します。減額する方法は、こちらも直接控除方式と間接控除方式の2つです。
次に、企業における減損会計の監査と内部統制について解説します。
減損会計の監査とは、減損損失の認識の判定や減損損失の測定に関する会計上の見積りの合理性や正確性を検証する監査のことです。
減損会計の監査には、以下のような手続きが必要です。
減損会計に関する重要な虚偽表示リスクを特定し、その原因や影響を分析する手続きです。
減損会計に関する重要な虚偽表示リスクに対応するために、十分かつ適切な監査証拠を入手する手続きです。
減損会計に関する重要な虚偽表示リスクの中でも、特に高いリスクを有するものに対して、追加的な監査手続を実施する手続きです。
減損会計の内部統制とは、減損会計に関する財務報告の信頼性を確保するために、経営者が設計し、実施し、維持する管理活動のことです。
減損会計の内部統制には、以下のような要素があります。
減損会計に関する経営者の姿勢や方針、組織構造、人事管理などの要素です。
減損会計に関する重要な虚偽表示リスクを特定し、その発生の可能性や影響の程度を評価する要素です。
減損会計に関する重要な虚偽表示リスクに対応するために、経営者が設定し、実施する具体的な管理活動の要素です。例えば、減損の兆候の判断基準や方法、減損損失の算定方法や仮定、減損処理の承認や記録などがあります。
減損会計に関する情報を適切に収集し、分析し、報告し、伝達する要素です。例えば、減損会計に関する方針や手順、減損の兆候や減損損失の見積りに関するデータや分析、減損処理の結果や開示などがあります。
減損会計に関する内部統制の有効性や適切性を定期的に検証し、必要に応じて改善する要素です。例えば、減損会計に関する内部統制の自己評価や監査委員会の監督などがあります。
最後に、IFRS(国際財務報告基準)と日本の減損会計の違いと課題について解説します。
IFRSと日本の減損会計の違いは、以下のような点があります。
日本では、市場価格が帳簿価額から50%以上下落している場合など、具体的な数値基準を設けているのに対し、IFRSではこのような基準はなく、より高度な実質的な判断が必要となります。
日本では、割引前将来キャッシュフローと帳簿価額を比較して減損の有無を判定し、減損が認識された場合には、帳簿価額を回収可能価額まで引き下げて減損損失を計算します。一方、IFRSでは、減損の兆候がある場合には、帳簿価額と回収可能価額を比較し、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、その差額を減損損失とします。
日本では、減損は原則として、特別損失として計上します。IFRSでは、特別損益と経常損益との区分がないため、営業損益に含めて計上します。
日本では、減損損失の戻入れは禁止されています。IFRSでは、減損損失の戻入れが可能ですが、のれんを除きます。
IFRSと日本の減損会計の課題は、以下のような点があります。
IFRSでは、減損の兆候の判断が主観的になりやすく、一貫性や比較性が低下する恐れがあります。日本では、減損の兆候の判断が保守的になりやすく、減損のタイミングが遅れる恐れがあります。
IFRSでは、減損損失の計算に割引率を用いるため、割引率の選択や変更が減損損失に大きな影響を与える可能性があります。一方、日本では、減損損失の計算に割引率を用いないため、将来のキャッシュフローの時間的価値を考慮できない可能性があります。
IFRSでは、減損が営業損益に含まれるため、減損のタイミングや規模によって、営業利益率やROEなどの財務指標に大きな影響を与える可能性があります。一方、日本では、減損が特別損失に含まれるため、減損の影響が営業活動と区別される可能性があります。
IFRSでは、減損損失の戻入れが可能であるため、減損の計上と戻入れの繰り返しによって、財務諸表の信頼性や透明性が低下する恐れがあります。一方、日本では、減損損失の戻入れが禁止されているため、減損の計上が過度に保守的になる恐れがあります。
このように、企業が保有する固定資産は、市場環境や技術革新などの影響で価値が低下する可能性があるものです。そこで必要となるのが、固定資産の減損会計です。
ただし、減損会計の処理や手続きは複雑であるため、クラウド会計システムによる管理をおすすめします。
例えば、キヤノンITソリューションズが提供する経営基盤ソリューション「SuperStream-NX」では、固定資産およびリース資産の各物件管理をおこない、減価償却計算などのデータを統合会計(GL)に連携する機能を備えています。また、さまざまな減価償却方法にも対応しており、予測シミュレーション機能や豊富なレポートも利用可能です。
「SuperStream-NX」は、法改正にも迅速に対応しており、リース会計基準変更に伴う売買処理対応 (リース資産のオンバランス化)なども可能です。
これらの理由から、「SuperStream-NX」は非常に優れた選択肢となります。
そこで、まずはオンラインでお気軽に資料請求してみてください。
また、自社に必要なシステムの種類や選び方がわからない場合は、いつでもキヤノンITソリューションズにご相談ください。貴社に適したソリューションを提供いたします。
国内1万社以上が導入する「SuperStream-NX」。下記の動画では、クラウド活用、システム連携、法改正対応の3つのポイントを解説しています。ぜひご視聴ください。