
公認会計士 中田清穂の会計放談 2021.07.07 (UPDATE:2024.11.25)
中田 清穂(なかた せいほ)
今年度(2021年度)から実施されている中学校の学習指導要領に関し、文部科学省が公表した学習指導要領解説(社会編)で、経済分野の学習について以下の記述があります。
| 資金の流れや企業の経営の状況などを表す企業会計の意味を考察することを通して、企業を経営したり支えたりすることへの関心を高めるとともに、利害関係者への適正な会計情報の提供及び提供された会計情報の活用が求められていること、これらの会計情報の提供や活用により、公正な環境の下での法令等に則った財やサービスの創造が確保される仕組みとなっていることを理解できるようにすることも大切である。(下線筆者) |
中学校の学習指導要領の解説で「会計」という言葉が4回も使われているのです。
私は、「えっ? 中学校で『会計』の授業? それ、早すぎない?」ということで、正直驚きました。
経理関係のお仕事をされている方々は、私と同じように感じられた人も多いのではないでしょうか。
それは世の中の「会計離れ」を肌身で感じているからだと思います。

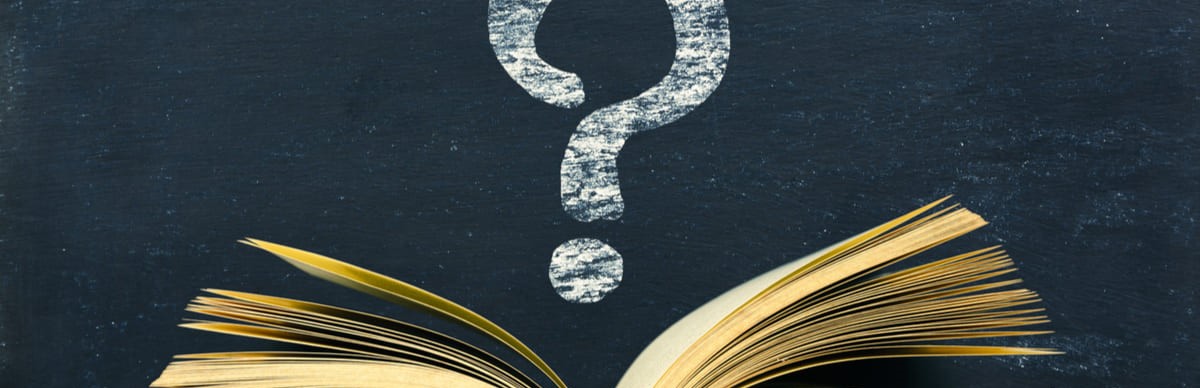
参考文献によれば、上記のような「会計離れ」の原因として、以下があげられています。
私としても、おおむね違和感がありません。
(1) 2006年1月の公認会計士試験制度の変更:
受験者数が大幅に増加し、合格者も大幅に増加しました。
しかし、試験に合格したものの、その約1割が監査法人等に就職できないという事態になりました。
そのことがマスコミで大きく報道され、公認会計士試験に合格しても就職できないという認識が
社会に広まってしまったようです。
(2) 大きな会計不祥事の発生:
2011 年のオリンパスの粉飾決算事案、2015 年の東芝の不適切会計事案などが続き、
大企業の会計や監査に対する信頼が損なわれました。
このことも、会計や監査に関する業務に対して悲観的に捉える傾向が続いているようです。
(3) 人工知能(AI)により公認会計士や税理士の仕事がなくなるという論文の発表:
2013年にオックスフォード大学のオズポーン氏が発表した論文
『雇用の未来~コンピューター化によって仕事は失われるのか~』ではAIが、
99%の確率で Tax Preparers(税務申告代行者)の仕事を奪い、
98%の確率で Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks(簿記、会計、監査担当員)の仕事を奪い、
94%の確率で Accountants and Auditors(経理担当者、監査人)の仕事を奪う
と予想しました。
これらの論文などにより、これから会計、経理、税務、監査の学習を開始しても、
将来、仕事がなくなってしまうという不安が広がったようです。
私は上記の原因に加えて、将来の仕事を考える若者たちに対する、彼らの親(保護者)の影響が強いのではないかと考えています。
すでに役職者や管理職になっている世代では、世の中の様々な情報をベースにして、会計関連の仕事に対して、強い不安感を抱いていると思います。
その彼らが、これから仕事を選択する上で、会計関連の仕事に興味をもつ若者たちを思いとどまらせているのではないかと思うのです。
最近では、入社式に参列を希望する親が続出しているという話も良く耳にします。
入社式の案内に、「ご父兄のご同伴はお控えください」と、わざわざ明記している会社もあるそうです。
両親の同伴の是非を言っているわけではありません。
それだけ親がわが子の就職や将来への関与度合いを強めている根拠の一つではないかということです。

以上のような状況で、今、中学教育で「会計」を取り上げる意味を考えたいと思います。
(1) 公認会計士や税理士などの専門家や経理担当者の増加が目的ではない。
「会計離れ」の原因の(3)で触れたように、会計・監査関連の仕事は、多かれ少なかれ、
AIやRPA(ロボティクス)にとって代わられると思います。
すでに、「紙」の請求書をPDF化して、それをAI-OCRでデジタルデータに変換して、
システムに登録するまでを自動化することは、実用的なレベルに達しています。しかも巨額の投資は必要ありません。
今後、令和3年度電子帳簿保存法の大改正やインボイス制度の改正により、この動きはどんどん加速していくでしょう。
「紙のエビデンス廃棄」を検討する企業数の増大は、様々なサーベイで明らかです。
したがって、「公認会計士や税理士などの専門家や経理担当者の増加」を目的とした教育は、
義務教育である中学では必要ないと思います。
では義務教育として教えるべき「会計」とは一体何なのでしょうか。
(2) 「会計」の何が大切なのかを教えること
人は、会社に限らず、学校、病院、役所、政党などいろいろな「組織」で活動します。
その組織活動は、金集め、人材集め、調査、宣伝、製造、開発、営業など、複雑多岐にわたります。
複雑な活動をする際に「金」は必ずつきまといます。
「会計」は、「勘定科目」という「道具」を使って、複雑多岐にわたる組織活動を「分類・整理する手続き」です。
「会計」の手続きで整理された、複雑多岐にわたる組織活動は、わかりやすくまとめられて、
将来のための判断に使われるのです。
「会計」を理解していない人は、組織の将来をどうしていくのか、
その判断に必要な情報の見極めができない人と言えます。
「会計」の専門家でなくても、財務・経理部門の人でなくても、
これまでの様々な「会計」の大切さがわからない人は、様々な活動の中で、何が無駄な活動で、
今後は無駄をなくすために何に気を付けなければならないのか、組織の目的・目標に向かって、
大切な「お金」をどこに使うべきなのかについて、理解できず、
いつまで経っても無駄のある活動をし続けることになるでしょう。
「会計」の大切さは、「数字の作り方」ではないのです。
「作られた数字の意味を理解して、判断に活かす」ことこそ大切なのです。
義務教育である中学教育で「会計」を教育することはとても良いと思います。
しかし、「数字の作り方」ではなく、「作られた数字の意味を理解して、判断に活かす」ことを
教育する方向であってほしいと願っています。
<参考文献>
本稿については、以下の論文を参考にしました。
『会計・税務人財育成に関する提案書~「会計離れ」を超えて~ 』
(会計・税務人財養成推進協議会 事務局 川野克典)
http://www.zb.em-net.ne.jp/~kawano/ATHRG/FinalReport.pdf
中田 清穂(なかた せいほ)
1985年青山監査法人入所。8年間監査部門に在籍後、PWCにて 連結会計システムの開発・導入および経理業務改革コンサルティングに従事。1997年株式会社ディーバ設立。2005年同社退社後、有限会社ナレッジネットワークにて、実務目線のコンサルティング活動をスタートし、会計基準の実務的な理解を進めるセミナーを中心に活動。 IFRS解説に定評があり、セミナー講演実績多数。