
トレンド情報 2021.11.09 (UPDATE:2024.11.22)
スーパーストリーム
【令和3年度】年末調整の電子化(ペーパーレス化)による変更点や導入のメリット・デメリット
令和2年度より、年末調整手続きの電子化(ペーパーレス化)が始まりました。
電子化によって、保険会社などから電子データで必要な情報を収集できるようになったため、従業員だけでなく、企業側の事務負担も大きく減少することが期待されています。
税制改正により、令和3年度も電子化の要件が緩和されることとなりますが、電子化の導入にあたっては、注意点をよく確認し、事前準備を行う必要があります。
今回は年末調整電子化について、令和3年度からの改正点や導入のメリット・デメリットについて解説します。
従来の年末調整では、従業員が各自の控除額などを手計算した申告書を作成し、控除証明書などの資料と合わせて紙媒体で勤務先へ提出する流れが一般的でした。
しかし所得税の改正によって税額計算が複雑化し、年末調整の際に作成する書類も増加したことによって、従業員側で正確な計算が困難となり、企業側の確認作業が増加することも懸念されていました。
また、以前より紙媒体での保管コストも問題視されていました。これらの背景から、令和2年10月以降の控除証明書の受領や各種申告書の作成については、紙媒体ではなく、電子上での手続きが可能となり、併せて電子データでの保管も認められるように変更されたのです。
電子化した場合の具体的な手続きは、まず従業員が「年調ソフト」によって各自の電子データを作成し、勤務先へ提出します。そして勤務先は提出を受けた電子データを自社の給与システムへ取り込み、年末調整計算を完了させる流れとなります。
令和3年度における年末調整電子化に関しては、以下の2つの変更が行われます。
年末調整で必要となる各種申告書をペーパーレス化するためには、あらかじめ税務署に対して承認申請を行い、税務署長の承認を受けることが要件とされていました。
しかし令和3年度の年末調整では上記の承認申請が不要となりました。いつでも好きなときに電子化を始めることができるように変更され、より電子化に取り組みやすい環境が整備されたと言えるでしょう。
従業員の中には、新居を購入し、住宅ローン控除の適用を受ける人も少なくありません。
令和2年度の年末調整では、住宅ローン控除を受けるために必要となる「住宅ローン控除申告書」については電子化の対象外とされていたため、別途紙媒体での提出が必要でした。
しかし令和3年度の年末調整より、「住宅ローン控除申告書」が電子化の対象に含まれ、電子化が可能な範囲が拡大されることになりました。また、「住宅ローン控除申告書」への押印も廃止になりました。
ただし居住年が平成30年以前の場合には、「住宅ローン控除申告書」や「年末残高等証明書」を電子データで提出することができないため、勤務先に対して紙媒体で提出しなければなりません。
年末調整を紙媒体ではなく、電子手続きで行うメリットは以下のとおりです。
・書類作成の手間が減少
・控除証明書などの再発行手続きが不要
従業員からすると、保険会社などから控除証明書を電子データで取得し、その電子データを「年調ソフト」に取り込むことによって、控除証明書の内容が申告書に自動入力されます。
そのため従来のように手書きで申告書を作成する必要がなく、また控除証明書を紛失してしまった場合の再発行手続きも不要となるのです。
・添付書類の確認や検算が不要
・給与システムへの入力作業が減少
・書類保管コストの削減
従業員から電子データで提出を受けることにより、企業側は控除証明書などの添付書類の確認や検算が不要となります。
また、提出を受けた電子データを給与システムへ取り込むことで年調計算が可能となるため、従来の手入力で行っていた作業が大幅に削減されることでしょう。
さらに電子化によってデータ保存が可能となるため、紙媒体の場合の保管コストを削減できます。
年末調整を電子化する場合、従業員と企業の双方において、
以下のような準備を進めなければなりません。
なお詳細については別記事で解説していますので、ぜひこちらのページをご参照ください。
(/column/zeimu-vol-134)
・「年調ソフト」のインストール
・ 控除証明書データの取得
勤務先へ提出する電子データを作成するためには、それぞれの従業員が専用の「年調ソフト」をインストールする必要があります。そして保険会社より控除証明書の電子データを取得し、勤務先へ提出する申告書テータを作成します。
・電子化実施の検討
・従業員への周知
従業員から電子データの提出を受けた段階では年末調整手続きは完了していません。従業員の電子データを企業側の給与システムに取り込み、年末調整計算を完結させる必要があります。
したがって、自社の給与システムが電子データの取り込みに対応していることが前提となります。
また、電子化が可能な環境かどうかをチェックした上で、導入する場合には従業員への周知やマニュアル整備を行いましょう。
年末調整手続きを電子化する場合、自社の業務効率化を目的とするケースが大半でしょう。
しかし電子データと紙媒体が混在する場合など、電子化の導入が必ずしも業務負担軽減へ繋がらず、かえって非効率な状態へ陥ってしまうことも十分に考えられます。
電子化の導入を検討する際には、以下のポイントを必ず確認しましょう。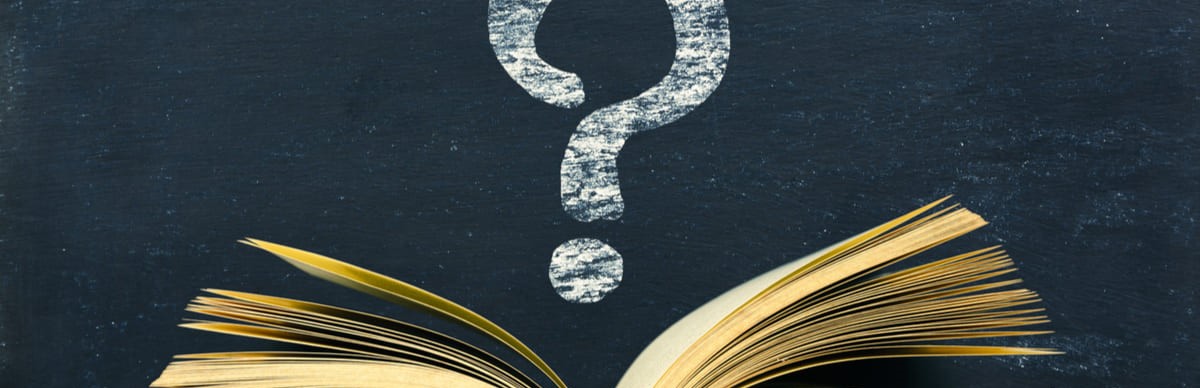
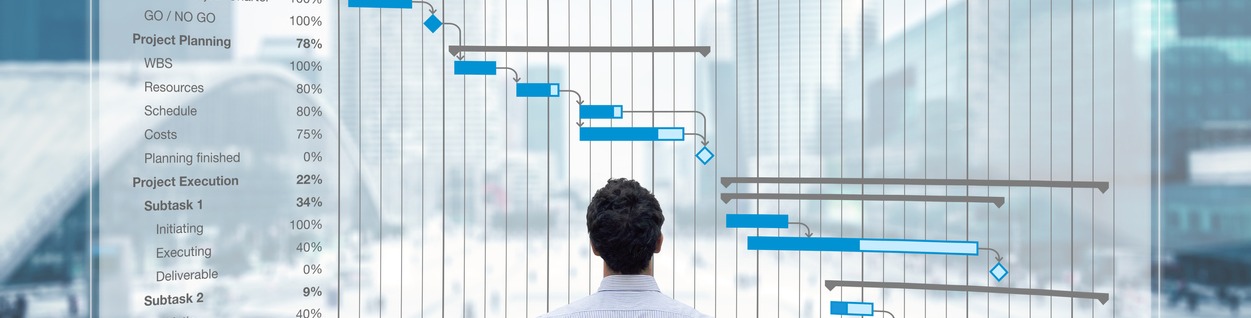
年末調整の電子化に関しては、「導入すれば必ず業務効率化が実現する」というものではありません。
従業員も含め、自社の環境を見つめ直し、電子化によるメリットが期待できるかどうか慎重に検討を重ねましょう。
業務効率化という観点においては、紙媒体と電子データが混在するのではなく、会社全体で統一的な運用を行うことが理想です。
しかし現状では、従業員規模が大きいほど手入力や紙媒体による作業が混在しやすく、電子上で手続きを完結させることは容易ではないでしょう。
したがって電子化を検討する場合には、自社で起こり得る様々なケースや従業員のITリテラシーをきちんと考慮し、電子化実施の可否を検討してください。
なお実施する場合には、必要に応じて社内研修やマニュアル整備を行うなどのフォロー体制を構築しましょう。
【税理士プロフィール】
服部大税理士事務所/合同会社ゆとりびと 代表社員
税理士・中小企業診断士
服部 大
2020年2月、30歳のときに名古屋市内にて税理士事務所を開業。
平均年齢が60歳を超える税理士業界の数少ない若手税理士として、顧問先の会計や税務だけでなく、創業融資やクラウド会計導入支援、補助金申請など、若手経営者を幅広く支援できるよう奮闘している。
執筆や監修業務も承っており、「わかりにくい税金の世界」をわかりやすく伝えられる専門家を志している。
事務所ホームページ:https://zeirishihattori.com
SuperStream製品についてご覧になりたい方は以下よりご確認ください。
※会計ソリューション案内はこちらより