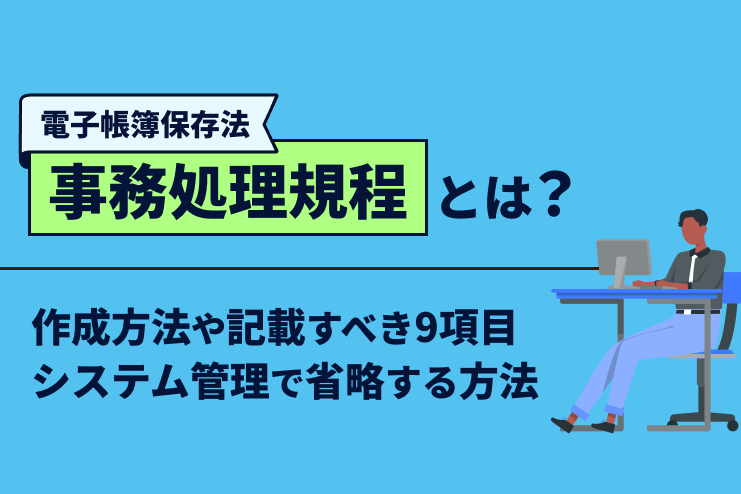
トレンド情報 2024.02.03 (UPDATE:2025.03.15)
スーパーストリーム
電子帳簿保存法とは、会計帳簿やその証憑書類を電子的に保存することを認めた法律です。
この法律により、紙媒体での保存義務がなくなり、経費の削減や業務の効率化が期待できます。しかし、電子帳簿保存法には、一定の条件や要件があります。
その一つが、事務処理規程の作成と届出です。事務処理規程とは、電子帳簿の保存方法や管理体制などを明確にした文書です。この文書には、必ず9項目を記載しなければなりません。しかし、システム管理することで、事務処理規程の作成そのものを省略することも可能です。
そこで今回は、電子帳簿保存法における事務処理規程の作成方法と記載すべき9項目や、システム管理で事務処理規定の作成を省略する方法を解説します。
企業の経理を担当する方は、ぜひ参考にしてください。
電子帳簿保存法における事務処理規程とは、電子取引のデータを保存する際に、訂正や削除の防止に関するルールを定めた書類のことです。
電子取引とは、電子メールやクラウドサービスなどを用いて、請求書や領収書などの書類を電子的に授受することです。
電子帳簿保存法では、2024年1月1日から、すべての事業者が電子取引のデータを保存する際に「真実性の確保」と「可視性の確保」を満たす必要があります。
「真実性の確保」には、タイムスタンプの付与や訂正・削除の履歴の確認などの方法がありますが、その中のひとつに、事務処理規程を定めて運用する方法があります。
電子帳簿保存法の保存要件とは、電子データで授受した取引情報を正しく保存するためのルールです。
保存要件には、次の3つの種類があります。
真実性の確保とは、保存したデータが削除や改ざんされていないことを証明するために、タイムスタンプを付与するなどの措置をとることです。
可視性の確保とは、保存したデータを検索や表示できるようにするために、関連書類やシステムの概要を備え付けることや、データをディスプレイやプリンタで出力できるようにすることです。
保存期間とは、保存したデータを一定期間保管することです。保存期間は、通常の帳簿書類と同じく7年間ですが、特別な事情がある場合は、それに応じて延長することができます。
電子帳簿保存法における事務処理規程の必要性とメリットには、以下のようなものがあります。
電子帳簿保存法では、電子データで保存する場合に「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件を満たす必要があります。そのうち「真実性の確保」の要件を満たすためのひとつの方法として、訂正や削除の防止に関する事務処理規程を定め、それに沿った運用を行うことが挙げられます。
事務処理規程を作成することで、電子取引データの管理や保存に関するルールを明確化し、税務調査に備えることが可能です。
事務処理規程を作成することにより、以下のようなメリットがあります。
事務処理規程を作成することで、社内でのルールが明確になり、スムーズな運用が可能です。また、人によって指示が異なる状況を防ぐことにもつながります。
電子帳簿保存法へ対応する際に、システムの導入が義務ではないため、予算をかけず対応できる点がメリットと言えるでしょう。
事務処理規程を作成することで、電子帳簿保存法の運用開始後に生じるトラブルの解決に役立つ可能性があります。例えば、管理責任者や対応方法を事前に定めておくことで、的確な指示や改善ができるでしょう。
電子帳簿保存法へ対応する際に、あらかじめ事務処理規程を作成しておくことで、幅広い取引に対応しやすくなるでしょう。
電子帳簿保存法における事務処理規程とは、電子取引で受けた証憑データの真実性を確保するための要件のひとつです。
事務処理規程には、以下の9項目を必ず記載する必要があります。
これらの項目について、具体的な内容と注意点を以下で説明します。
目的には、この規程が電子帳簿保存法第7条(電子取引)に関するものであることを明記します。
例えば「本規程は、電子帳簿保存法第7条(電子取引)に基づき、当社が行う電子取引に係るデータの訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程である」などです。
適用範囲には、この規程により処理を行う対象者の範囲を定めます。
例えば「本規程は、当社の全ての従業員に適用する」などです。
管理責任者には、事務処理規程における管理責任者を指定します。
管理責任者は、訂正・削除の申請や承認、記録や保存の監督などを行う人のことです。
例えば「本規程における管理責任者は、経理部長とする」などです。
電子取引の範囲には、法令における電子取引の範囲を説明し、自社で取り扱う電子取引の形態を具体的に示します。
電子取引とは、電子メールやクラウドサービスなどを用いて、請求書や領収書などの書類を電子的に授受することを指します。
例えば「本規程における電子取引とは、次のような方法で行われる取引を指す。EDI取引・
電子メールを利用した請求書等の授受・クラウドサービスを利用した請求書等の授受」などです。
取引データの保存には、保存するデータの場所と年数を定めます。
保存場所は、電子データの安全性や可視性を確保できる場所を選びましょう。保存年数は、法令に基づき、最低7年間とします。
例えば「保存するデータの場所と年数は、次のとおりとする。保存場所は当社のサーバー、保存年数は7年間」などです。
対象となるデータには、電子取引対象として保存する情報を定めます。
対象となるデータは、見積書や請求書、発注書、納品書、領収書など、取引に関する書類やデータを含みます。
例えば「対象となるデータは、次のとおりとする。見積書・請求書・発注書・納品書・領収書」などです。
運用体制には、保存する情報の管理責任者と処理責任者を指定します。
処理責任者とは、実際に訂正・削除の処理を行う人のことです。
訂正・削除がある場合、処理責任者は訂正・削除申請書を管理責任者に提出し、管理責任者の指示のもと処理責任者が訂正・削除の処理を行います。そのため処理責任者は、訂正・削除の処理から最終的な保管までを行うことになります。
例えば「保存する情報の管理責任者と処理責任者は、次のとおりとする。管理責任者は経理部長、処理責任者は経理部担当者とする」などです。
訂正削除の原則禁止には、保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする旨を記載します。
例えば「保存する取引関係情報の内容について、正当な理由がない限り、訂正及び削除をすることは禁止とする」などです。
訂正削除を行う場合には、やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正や削除する場合の処理方法を定めます。
訂正や削除ができる条件、その方法について社内フローや利用するシステムなど詳細を明記します。
例えば「保存する取引関係情報を訂正・削除する場合は、次の手続きを行う。
などです。
事務処理規程の作成例とサンプルについては、国税庁の参考資料をまとめたWebサイトがありますので、ぜひご参照ください。
電子帳簿保存法の事務処理規程は、作成に時間と手間がかかるだけでなく、訂正や削除の申請や記録などの手続きも煩雑です。そこで、事務処理規定を作成せずに電子帳簿保存法に対応する方法として、スーパーストリームのクラウド会計システム「SuperStream-NX統合会計」がおすすめです。
「SuperStream-NX統合会計」は、SuperStream(スーパーストリーム)の会計・人事給与システムのクラウド版です。SuperStreamは、国内の大企業から中堅企業を中心に、約10,000社を超える企業から支持されています。
「SuperStream-NX統合会計」を導入することで、次のようなメリットがあります。
システム化により、電子データの訂正や削除の防止や確認が容易となり、業務効率が向上するでしょう。
また、システム連携ツールを利用することで、クラウド環境からセキュアな形でオンプレミスのデータを参照・取得したり、クラウドサービス同士のシステム連携が容易にできます。
さらに、ソフトウェア資産を持たずに基幹システムを運用できるので、導入費用や運用費用などのコストを削減できるのも魅力です。
そこで、電子帳簿保存法に最適なクラウド会計システムを選択したい方におすすめしたいのが、キヤノンITソリューションズの「SuperStream-NX」です。
「SuperStream-NX」は、クラウド会計システムとして多くの企業に選ばれています。
高度な機能と操作性を備え、コスト削減や保守・管理業務の負担軽減が可能です。さらに、高いセキュリティと可用性を提供し、ビジネスの成長に応じた柔軟な拡張性も魅力です。
AI-OCRを活用した業務の自動化と効率化も実現しており、手作業によるミスを減少させ、業務効率を大幅に向上させることが可能です。
これらの理由から、「SuperStream-NX」は非常に優れた選択肢となります。
そこで、まずはオンラインでお気軽に資料請求してみてください。
また、自社に必要なシステムの種類や選び方がわからない場合は、いつでもキヤノンITソリューションズにご相談ください。貴社に適したソリューションを提供いたします。
国内1万社以上が導入する「SuperStream-NX」。下記の動画では、クラウド活用、システム連携、法改正対応の3つのポイントを解説しています。ぜひご視聴ください。