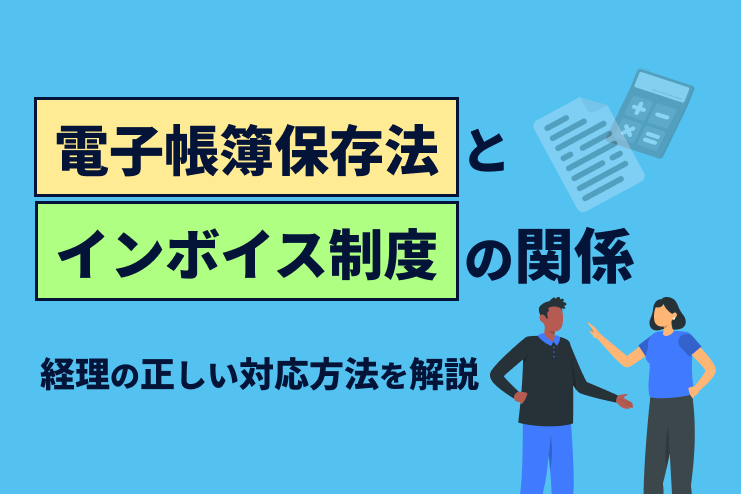
トレンド情報 2024.02.04 (UPDATE:2025.03.15)
スーパーストリーム
2023年10月1日から導入されたインボイス制度は、消費税の課税事業者が適格請求書(インボイス)を発行することで、消費税の納付や還付をスムーズに行えるようにする制度です。
このインボイス制度には、電子帳簿保存法に基づく電子化の義務や、インボイスの発行・受領・管理のルールなど、経理担当者が注意すべきポイントが多くあります。また、2024年1月1日からは、改正電子帳簿保存法が施行されるため、両方の制度に従って経理を行うことが重要です。
もし、双方に適切に対応できなければ、消費税の納付や還付が適切にできないだけでなく、税務調査で不利になる可能性があるため、十分な注意が必要です。
そこで今回は、電子帳簿保存法とインボイス制度の関係や、経理の正しい対応方法を詳しく解説します。企業の経理を担当する方は、ぜひ参考にしてください。
まずはじめに、インボイス制度と電子帳簿保存法の概要と目的について解説します。
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の要件として、インボイス(適格請求書)に記載された消費税額のみを控除できる制度です。
インボイスは、登録事業者のみが発行できる請求書などを指しますが、一定の事項が記載されていなければなりません。
インボイス制度の目的は、消費税の正確な計算と納付を促進し、税務行政の効率化と公正化を図ることです。
一方、電子帳簿保存法とは、税務関係の帳簿や書類を電子データで保存することを認めた法律です。
電子帳簿保存法は、電子帳簿保存、スキャナ保存、電子取引データ保存の3つの区分に分かれています。その中でも、電子取引データの保存は2023年12月末までの移行期間を経て、2024年1月1日から義務化されます。
電子帳簿保存法の目的は、経理のデジタル化を推進し、事業者の経営効率化と環境負荷の低減を図ることです。
インボイスを電子データで交付・受領・保存する場合は、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。これには、電子取引データの真実性と可視性の確保、関連書類の備え付け、検索機能の確保などが含まれるため、注意が必要です。
インボイス制度では、3万円未満の少額取引についても請求書や領収書を保管しなければならないため、経理部門で処理すべき証憑が大幅に増える可能性があります。これに対応するためには、電子帳簿保存法に対応したクラウド会計システムの導入が有効です。
インボイス制度と電子帳簿保存法は、同時に対応しておくと安心です。インボイス制度は2023年10月から開始されていますが、電子帳簿保存法の移行期間も2023年12月末までとなっているため、インボイス制度への対応と同時に、電子帳簿保存法の要件も考慮しておく必要があります。
インボイスとは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるための請求書などのことです。
インボイスには、区分記載請求書に必要な事項に加えて、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額などが記載されます。
インボイスの様式は法令や通達で定められておらず、必要な事項が記載された書類であれば、名称や形式は問われません。
インボイス発行事業者となるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。なお、登録申請書の提出には、e-Taxの利用が可能です。
インボイス発行事業者に登録されると登録番号が通知され、国税庁の公表サイトに登録情報が掲載されます。
※国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトはこちら。
インボイス発行事業者には、原則として、取引の相手方(課税事業者に限ります)の求めに応じて、インボイスを交付する義務があります。また、交付したインボイスに関しては写しの保存が義務づけられているため、注意が必要です。
このように、インボイスを交付された課税事業者は、一定の事項を記載した帳簿とインボイスを保存することが、仕入税額控除の要件となります。
電子帳簿保存法とは、税務関係の帳簿書類を電子データで保存できるようにする法律です。
保存義務と要件は、電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引の3つの区分によって異なります。
電子帳簿保存法の改正により、2024年1月1日からは電子取引のデータ保存が原則義務化され、紙での保存ができなくなります。また、スキャナ保存や電子帳簿等保存の要件が緩和された点にも注意が必要です。
電子帳簿保存法の対象は、原則として全ての法人と個人事業主です。ただし、一定の例外があります。例えば、電子取引のデータ保存については、相当の理由によってシステム対応ができない事業者は、2024年以降も紙での保存が可能です。
また、電子帳簿等保存の例外として、手書きで作成した国税関係帳簿や国税関係書類は対象外となります。この場合は、紙のまま保存するか、スキャンして画像データで保存することも可能です。
インボイス制度と電子帳簿保存法の対応方法としては、主に次の3つが重要となるため、それぞれ解説します。
電子インボイスの発行者(売手)は、消費税法で定められた適格請求書の要件を満たす必要があります。また、提供した電子インボイスについては、電子帳簿保存法に準じて一定の要件を満たした方法で保存する必要があります。
電子インボイスの提供を受けた事業者(買手)は、その電子インボイスを一定の要件を満たした方法で保存することで、仕入税額控除の適用を受けることが可能です。
ただし、電子インボイスの受領を確認するための手続き(タイムスタンプや要件を満たすシステムの使用など)が必要です。
電子インボイスは、発行者と受領者ともに、原則として課税期間の末日の翌日から7年間の保存が必要です。
電子インボイスの確認・検索・管理の方法として、次の3つの点に注意しましょう。
電子インボイスを確認する際は、受領したインボイスまたは簡易インボイスに必要な8項目が記載されているか確認しましょう。また、インボイスを発行した事業者が適格請求書発行事業者として登録済みであるかどうかがわからない場合には、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで登録番号を入力することで検索が可能です。
電子インボイスの検索とは、電子インボイスの検索性を確保するために必要な処理方法です。具体的には、取引内容や取引年月日などのキーワードで保存した電子インボイスを検索できるように、データを整理・管理することです。また、電子インボイスのデータは、紙に印刷して保存することができなくなるため、パソコンやシステム内で適切に保存する必要があります。
電子インボイスの管理には、データの訂正や削除を防止するための措置が必要です。具体的には、タイムスタンプを付けることや、訂正削除について一定の要件を満たすシステムを使用すること、売り手と買い手がデータ訂正削除の防止に関する事務処理規程を設けるなどの方法があります。また、電子インボイスのデータは、原則として約7年間保存する必要があります。
電子インボイスの訂正・削除・取消の対処法として、次の3つのポイントを押さえておくことが重要です。
適格請求書の記載事項に誤りがあった場合は、売り手は修正した適格請求書を買い手に改めて交付する必要があります。
なお、修正した適格請求書の交付方法には、以下の2つがあります。
適格請求書の交付後に取引が取消された場合は、売り手が適格返還請求書を買い手に交付する必要があります。
なお、適格返還請求書とは、適格請求書と同じ記載事項を持ち、取引の取消を明示するものです。
適格請求書の交付後に取引が一部取消された場合、売り手は適格請求書の交付額を減額する必要があります。
減額の方法には、以下の2つがあります。
スーパーストリームの「SuperStream-NX統合会計」は、国内で高いシェアを誇る会計システムで、大手企業を中心に10,000社以上の導入実績があります。
「SuperStream-NX統合会計」は、インボイス制度に対応した適格請求書の作成・交付・管理ができるクラウド会計システムで、スーパストリームが長年培ってきたノウハウと最新のテクノロジーを結集し、企業のバックオフィスの最適化を実現します。
「SuperStream-NX統合会計」の特徴は、その使いやすさと柔軟性の高さにあります。例えば、Webインターフェースによって提供されるクラウドサービスであるため、あらゆるデバイスからWebブラウザを経由してアクセス可能です。また、スーパストリームは、オンプレミスからクラウドまで、柔軟な導入形態でお客さまの環境に適したサービスを提供しています。
「SuperStream-NX統合会計」を導入するメリットは、法改正への迅速な対応と強力なセキュリティ対策にあります。スーパーストリームのクラウド会計システムを導入すれば、サーバやソフトウェアの保守、法改正への対応といった煩わしさからも解放されます。
特に、電子帳簿保存法に対応するために、証憑管理やAI-OCR等のオプションによる経理の定型業務の自動化機能も提供しており、さらにバックアップや暗号化などのセキュリティ対策も万全です。これらにより、データの安全性を高めることができるでしょう。
このように、インボイス制度や電子帳簿保存法に最適なクラウド会計システムを選択・導入したいとお考えの方には、キヤノンITソリューションズの「SuperStream-NX」です。
「SuperStream-NX」は、クラウド会計システムとして多くの企業に選ばれています。
高度な機能と操作性を備え、コスト削減や保守・管理業務の負担軽減が可能です。さらに、高いセキュリティと可用性を提供し、ビジネスの成長に応じた柔軟な拡張性も魅力です。
AI-OCRを活用した業務の自動化と効率化も実現しており、手作業によるミスを減少させ、業務効率を大幅に向上させることが可能です。
これらの理由から、「SuperStream-NX」は非常に優れた選択肢となります。
そこで、まずはオンラインでお気軽に資料請求してみてください。
また、自社に必要なシステムの種類や選び方がわからない場合は、いつでもキヤノンITソリューションズにご相談ください。貴社に適したソリューションを提供いたします。
国内1万社以上が導入する「SuperStream-NX」。下記の動画では、クラウド活用、システム連携、法改正対応の3つのポイントを解説しています。ぜひご視聴ください。