
トレンド情報 2023.01.11 (UPDATE:2024.11.20)
スーパーストリーム
現在では、企業の業務にデータやデジタル技術を活用することも決して珍しくありません。
業務へのデータやデジタル技術活用のひとつとして、バックオフィスDXがあり、業務効率化の有効な手段として注目されています。
当記事では、企業におけるバックオフィスDX導入のメリットや課題、成功のポイントなどについて解説を行っています。
バックオフィスDXの導入を考えている方や、業務効率化を考えている方はぜひ参考にしてください。
営業や受付、コールセンターなど顧客と直に接する業務をフロントオフィス業務と呼びます。また、フロントオフィス業務に対して、経理や総務、人事といった直に顧客と接することのない業務をバックオフィス業務として、両者を区別しています。
企業における事務部門として、企業の顔となるフロントオフィス業務を後方からサポートすることが、バックオフィス業務の役割です。バックオフィス業務は、顧客と接し直接利益を生み出す営業のような派手さはありません。しかし、企業活動が円滑に行われるようにサポートする裏方としての重要な役割を担っています。
フロントオフィス業務とバックオフィス業務は、企業における両輪の関係ですので、どちらかが欠ければ企業活動は立ち行かなくなるでしょう。
つまり、両者のバランスが取れてこそ、最大限の効果が発揮できるということです。
DXとは、「Digital Transformation(デジタル・トランスフォーメーション)」の略称で、業務や組織に対してデータやデジタル技術を取り入れることによるサービスやビジネスモデルの改革や変革を指します。
DXは業務効率化だけでなくビジネスモデル自体の改革まで進める方法であり、既存プロセスの効率化を図るIT化とは区別されます。
参考として、経済産業省が公開している「デジタルガバナンス・コード2.0」におけるDXの定義を見てみましょう。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」
参考:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc2.pdf
DXの定義は上記の通りです。
では、バックオフィスDXはどうでしょうか?
バックオフィスDXは、経理や総務といったバックオフィス部門に対してデータやデジタル技術を導入することで業務効率化を図るのが目的です。
DXの定義をふまえると、製品やサービス、ビジネスモデル自体の変革も目的に含まれます。バックオフィス業務は直接利益を生み出す部門ではありませんが、バックオフィスDXの導入はフロントオフィス業務を含めた企業全体の業務効率化につながるため、サービスやビジネルモデルの変革、さらには企業経営の改善にもつながるでしょう。
バックオフィスDXが注目されているのは、業務の効率化に有効といった理由だけではありません。
業務効率化の他に、バックオフィスDXが注目されている大きな理由として「2025年の崖」が存在します。
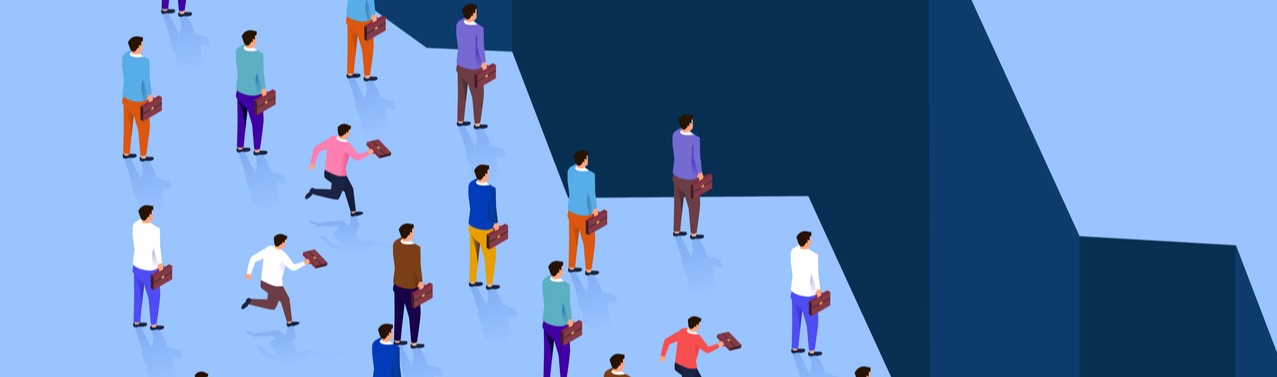
「2025年の崖」とは、2018年9月に経済産業省が発表したDXレポートにおいて提起された問題です。
経済産業省はDXレポート内において、2025年までに企業におけるDX導入が進まなかった場合に、発生する経済損失を最大で年間12兆円と試算しています。
レポートでは、ビジネス環境の変化に対応しきれず競争力を失えば巨額の損失が発生するとしている一方で、DX導入が進めば、壁を打ち破り損失を回避することが可能であるとして、対策の必要性を強調しています。
現代の目まぐるしく変化するビジネス環境には、老朽化、肥大化、複雑化、ブラックボックス化した旧態依然のレガシーシステムのままでは対応できません。
また2025年には、旧来のシステムを保守している人材の多くが退職する時期でもあります。既存システムの保守が困難となっていることに加え、2025年には業務を支えるソフトウェアの多くがサポート切れとなる予定で、企業は対応に迫られています。
2025年には市場のデジタル化もより一層進んでいると予想され、レガシーシステムのままでは競争に打ち勝つのは難しいでしょう。ひとつの大きな区切りとなる2025年に向け、DXによる既存システムの改革や変革は急務です。
こうした理由から、バックオフィスDXを含めたDXによるレガシーシステムの改革が注目を集めています。
参考:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_03.pdf
「2025年の崖」の要点と対応のポイントについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
「2025年の崖」とは?DX推進に向けた課題と回避するためのポイント
企業がバックオフィスDXを導入した場合のメリットには、「業務の効率化」「コスト削減効果」「多様な働き方による人材確保」などが挙げられます。
各メリットの内容については、項目ごとに解説を行います。
バックオフィス業務は、経理や総務、人事など多岐に渡り、その業務内容も部門ごとに異なります。
しかし、業務の中には、定型的なルーチン業務も多く含まれており、自動化することで業務の大幅な効率化が図ることが可能です。
また、定型業務以外でも法務部門における契約書のチェックをDXの導入により効率化すれば、チェックミスの軽減にもつながり、コンプライアンス向上にも寄与します。
ルーチン業務やチェック作業などを自動化、効率化することで、それまで業務に必要とされていた時間の短縮が可能です。
たとえば、残業や休日出勤を行わなければ処理できなかった業務が所定労働時間内で処理できるようになれば、人件費をはじめとしたコストの削減効果が望めます。
ルーチン業務を外部に委託している企業であれば、自社でのバックオフィスDX導入により外注費の削減効果も見込めます。
バックオフィスDXを導入することで、バックオフィス業務においてもITツールを活用した場所を問わない多様な働き方が可能となります。コロナ禍以降、急速に普及拡大したテレワークやリモートワークは、その典型例です。
バックオフィス業務のデジタル化で出社が不要となり、在宅での勤務が可能となれば、それまでは難しかった育児や介護と仕事の両立が図りやすくなります。
育児や介護といった家庭事情を原因とする離職は企業の悩みのひとつですが、バックオフィスDXの導入により、育児や介護に伴う離職を減らす効果も期待できるでしょう。
家庭と仕事の両立が可能な職場は、求職者にとって魅力的に映るため、優秀な人材の確保につながる点も見逃せないメリットです。また在宅での勤務が可能となれば、それまで出社にかかっていた時間を余暇の時間に当てることも可能となり、社員のモチベーションアップにもつながります。

バックオフィス業務にDXを導入するためには、まず書類のペーパーレス化から始めることがお勧めです。
書類を紙媒体からデジタル媒体に変更することで保管用のスペースが不要となり、書類の検索性も大きく向上します。
また、デジタル化によって書類の共有も容易となり、作業における場所的な制限も少なくなります。
デジタル文書への移行は、従来の作業が手軽に行えるだけでなく、それまで紙媒体で行っていた作業がデジタル化されるため、わかりやすく変化を感じられるでしょう。
バックオフィス業務にDXを導入する方法としては、クラウドサービスやRPA(Robotic Process Automation)の活用なども挙げられます。クラウド給与計算ソフトを利用すれば、場所を問わず業務が可能となり、法改正への対応も容易です。
またRPAは、これまで人間のみが対応可能とされてきた作業指示書やレポートの作成など、複雑な作業も機械学習による自動化が可能となっており、活用によって大きな効果が見込めます。

バックオフィスDXは、導入に当たって解決しなければならない課題も存在します。
「不透明な経営戦略」「デジタル知識のある人材の不足」「投資の不足」が主な課題です。
以下に項目ごとの解説を行います。
課題のひとつとして、バックオフィスDXの導入に当たり、適切な経営戦略の策定が困難であるということが挙げられます。
導入に当たって適切な経営戦略が策定できなければ、適切なバックオフィスDXの導入も不可能です。
しかし、導入の必要性は理解できても、経営陣のDXに対する理解不足から具体的に何を行えば良いのか判断できず、不透明な経営戦略になってしまうケースが見られます。
不透明な経営戦略は、そのままDX導入の失敗へとつながるため、導入に当たり、まず解決しなければならない課題となっています。
知識を持つ特定の人材しか扱えない、あるいは自社に合わないツールやシステムを選んでしまうと、運用が限定的になります。属人化すると人材育成や引き継ぎにも影響してくるでしょう。
バックオフィスDXの推進には、自社に合ったツールやシステムの導入が不可欠です。
ただし、扱いやすいシステムであっても、社内でDXを推進するためには、デジタル知識のある人材が必要となります。
自社内に人材が確保できていれば問題ありませんが、人材が存在しない場合には、外部への委託か、自社内で人材を育成することになります。外部への委託はコストが掛かりますし、教育には時間が掛かるため、導入には人材面での課題も解決しなければなりません。
経営戦略や人材の他に、バックオフィスDXの導入に必要となる投資が不足することも課題として挙げられます。
バックオフィスDX を推進するには、レガシーシステムの改革が必要となりますが、時代に合ったシステムに再構築するためには、少なくない額の投資が必要です。
既存のレガシーシステムの保守にもコストが掛かるため、システムの再構築に割くリソースがなく、DX導入を諦めざるを得ないケースも見られます。
自社に不要な機能は省き、自社の規模に合ったシステムを選定するなど、コスト面での工夫も必要です。
バックオフィスDXの導入には、クラウドサービスやRPAの活用など様々方法があります。
しかし、どのような方法でバックオフィスDXを導入するにせよ、自社に合った形でなければ意味がありません。
そのため、導入に当たっては自社に何が必要であるかを判断するために、まずは業務の洗い出しを行い、問題を可視化することが必要です。

扱いやすいシステムを導入することもバックオフィスDXを成功させる上で大事な要素となります。
多機能であっても自社の社員が使いこなせなければ意味がありません。システムを選定する際は、操作性の良さやわかりやすさをチェックしておきましょう。
ただし、扱いやすいシステムであっても、これまでとは全く異なった作業を要求されて社員が戸惑う場合もありますので、社員への教育やアフターフォローを整えておくことも必要です。
状況によっては、外部講習会への参加や外部専門家の協力を仰ぐことも検討してください。
また、いきなり全業務を対象としたバックオフィスDXを導入するのではなく、ペーパーレス化など導入しやすい方法から取り入れる小規模限定的なスモールスタートを行うことも、成功させるポイントのひとつです。
バックオフィスDX推進のためのサービスやシステムは数多くありますが、一例として、スーパーストリーム社が提供する「SuperStream-NX」を紹介します。
「SuperStream-NX」は、企業のバックオフィス業務の最適化を目的としたシステムで、バックオフィス業務の中核である財務会計・人事給与分野の最適化を強力にサポートします。
「経理部・人事部ファースト」の思想を取り入れ、高度な機能と使いやすさの双方を実現したシステムです。
自社においてバックオフィス業務にDXを導入したいけど、どのサービスを利用すれば良いのかわからないと考える企業担当者は、ぜひ「SuperStream-NX」の導入を検討してみてください。
「SuperStream-NX」の特長や機能について詳しくは、下記のページをご参照ください。
/product
経済産業省がDXレポートにおいて提起した「2025年の崖」は、企業に少なからず衝撃を与えました。
そのため、危機感を持った多くの企業は、自社へのDX導入を行い、業務の効率化に努めています。
バックオフィスDXを含めたDXの導入は、企業における既存システムの変革や改革をもたらし、業務の効率化に大きく寄与しています。しかし、DXの導入には課題も多く、成功させるには入念な準備が必要です。
当記事では、バックオフィスDX導入の課題と成功のポイント、DX推進にお勧めのシステムなどについて解説を行ってきました。
これからDX導入を考えている方はもちろんのこと、自社におけるDX導入が上手く行っていないと感じている方も、ぜひ当記事を参考にして、DX導入を成功させてください。
「ヒト」「モノ」「カネ」といった企業資源を管理する人事や総務、経理といったバックオフィス部門は、企業活動を後方から支援しています。
バックオフィス部門が、有効に働いていなければ、営業などのフロントオフィス部門が円滑に活動することはできません。
事務方であるバックオフィス部門が扱う業務は、多岐に渡りますが、全てが高度な判断を要するわけではなく、定型化されている業務も多くなっています。これまで手作業で行ってきた定型的業務をバックオフィスDXの導入により自動化できれば、大幅な効率化が望めます。
人材不足や資金的な問題から、未だにDXが導入できていない企業も多くなっています。
しかし、2025年の崖まで時間的猶予は少なく、DXの導入によるレガシーシステムからの脱却は喫緊の課題です。まずは取り組みやすい書類の電子化などから、DXを導入してみてはいかがでしょうか。
【監修者プロフィール】
社会保険労務士
涌井好文(涌井社会保険労務士事務所代表)
平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。
近時はインターネット上でも活発に活動しており、クラウドソーシングサイトやSNSを通した記事執筆や監修を中心に行っている。
SuperStream製品についてご覧になりたい方は以下よりご確認ください。
※人給ソリューション案内はこちら
※会計ソリューション案内はこちら