
トレンド情報 2023.10.24 (UPDATE:2025.04.15)
スーパーストリーム
繰延税金資産とは、企業会計と税務会計の間で期間的なズレが生じた場合に、企業会計上の税務費用を適切に対応させるための会計処理である「税効果会計」で使用する会計科目です。
この繰延税金資産は、いつでも無条件で計上できるわけではなく、回収可能性を検討する必要があります。なぜなら、将来減算する課税所得が見込めないとき(つまり赤字になった場合や業績が低迷するような事態に陥ったときなど)は、繰延税金資産の取り崩しを実行することになり、決算に影響を与えるためです。
このように、繰延税金資産は、企業の会計処理において重要な要素の1つと言えるでしょう。
そこで今回は、繰延税金資産についての取り崩しや回収可能性、仕訳方法などを徹底解説します。企業の経理を担当する方は、ぜひ参考にしてください。
繰延税金とは、企業会計と税務会計の間で期間的なズレが生じた場合に、企業会計上の税務費用を適切に対応させるための会計処理である「税効果会計」で使用する概念です。
繰延税金は、企業会計上の税務費用と税務会計上の負担金額に差異がある場合に発生します。この差異を解消するために、企業会計上に「繰延税金資産」を計上し、将来的に課税所得から減算される額を示します。
繰延税金資産については、取り崩しや回収可能性、仕訳方法などを理解することが重要です。
税効果会計とは、企業会計と税務会計のズレを調整する手続きのことです。企業会計と税務会計では、収益と費用、または益金と損金の認識時期や考え方が異なるため、その差異によって生じる不整合を調整する目的で税効果会計が導入されています。
企業会計とは、主に営利企業に適用される会計手法であり、企業の業績を正確に把握するために収益から費用を引いて企業の利益を求めます。一方、税務会計とは、税法の規定に従って処理する会計手法のことで、公平な課税を目的に行うものです。
この税効果会計は、すべての企業が必ず適用しなければいけないものではありません。税効果会計の適用義務があるのは、主に上場企業や金融商品取引法の適用を受けている非上場企業、そして会社法上の大企業のみとなります。
下記の資料では、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」について、公認会計士がわかりやすく解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。
繰延税金資産とは、企業会計と税務会計の間で期間的なズレが生じた場合に、企業会計上の税務費用を適切に対応させるための会計処理「税効果会計」で使用される会計科目です。
また、企業会計上の収益と費用、税務会計上の益金と損金では、それぞれ認識にあたって期間的なズレが生じることがあります。このズレが解消されないものを「永久差異」と言い、認識時期が違うだけで将来的に解消されるものは「一時差異」と呼ばれます。
繰延税金資産は、税効果会計の一時差異のうち、将来課税所得が減額されると予測される額を表します。これは税務会計上の計算で、利益が企業会計上の計算よりも上がったことによるズレです。
例えば、賞与引当金や貸倒引当金の法定限度額の超過分が損金に算入されないことなどが、繰延税金資産の発生原因にあげられます。
企業会計上の資産・負債と、税法上の資産・負債では、それぞれの認識や計上できるタイミングが異なります。この違いにより、実際は経費として支出している費用が税務上の経費扱いとならず、その分税金を多く支払う場合があります。このようなケースでは、支払う税金の超過額を「繰延税金資産」として計上し、翌年度の課税所得から控除される仕組みです。
上記を簡単に言えば、繰延税金資産とは「税金の前払い」と考えることができるでしょう。
例えば貸倒引当金は、企業会計上は計上できる金額を計上していても、税法上は損金算入限度額(税務上損失として処理できる限度額)を超えた分は損金として認められません。
この場合、税金の支払いが生じた超過額を「繰延税金資産」として計上することで、翌年度の課税所得から控除され、その分だけ法人税額が減少します。
ただし、繰延税金資産は無条件で計上できるわけではなく、回収可能性を検討することが必要です。将来減算する課税所得が見込めないとき、つまり赤字になった場合や業績が低迷するような事態に陥ったときなどは、繰延税金資産の取り崩しを実行することになります。これは、繰延税金資産の取り崩しが決算に影響を与えるためです。実際に多額の繰延税金資産が取り崩されて費用に計上されることで、もともとは赤字ではなかった企業が最終赤字を計上するといったケースもあります。
下記の資料では、多岐に渡る業務のなかで常にスピード感と質の両軸が求められている経理・財務部門の主な「11の課題」について、どのような対応が必要かを分かりやすく解説します。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。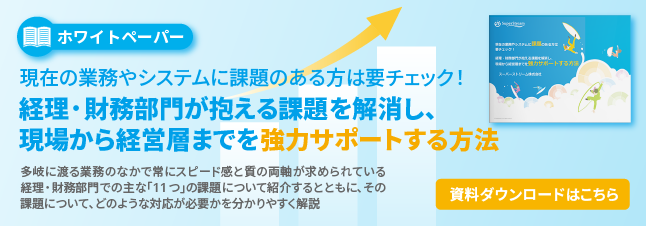
永久差異と一時差異は、企業会計と税務会計の考え方の違いから生じる差異です。
永久差異は、費用と収益、税務会計の損金と益金に対する捉え方が違うことで生じる差異であり、将来においても費用と収益、損金と益金の間の差異は解消されません。
一方、一時差異は、費用と損金、収益と益金の認識時期が異なるために生じるものです。一時差異は将来いずれ解消するため、税効果会計を採用して税金を期間配分することが求められます。
繰延税金資産は、将来の税負担が軽減される額を資産として計上するもので、実質的に法人税等の先払いを意味します。繰延税金資産の取り崩しとは、将来減算する課税所得が見込めなくなった時点で、会計上も解消する処理を行うことを指します。
繰延税金資産は、以下の式で計算可能です。将来減算一時差異を集計し、その合計額に法定実効税率を乗じることで、繰延税金資産の金額が求められます。
法定実効税率とは、企業が利益に対して実質的に負担する税率のことで、以下の算式で計算できます。
※事業税に標準税率を適用する場合
下記の資料では、会社の経営状況を表す財務諸表のうち、売上・利益等の業績を明らかにする損益計算書について、わかりやすく解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。
繰延税金資産の対象になるのは、利益を課税標準にした税金のみとなります。 具体的には、法人税、均等割を除く住民税、課税標準を利益とする事業税の所得割、地方法人特別税です。
一方、住民税の均等割や課税基準が収入の事業税、事業税の付加価値割と資本割、事業所税などは、繰延税金資産の対象にはなりません。
これは、繰延税金資産そのものに資産価値がないためで、企業の利益を課税標準とした税金のみが繰延税金資産の対象として認められる要因です。
繰延税金資産が計算できれば、次に仕訳を行います。仕訳する際の相手勘定は、法人税等調整額という科目です。
繰延税金資産は、下記のように貸借対照表の流動資産と固定資産に分かれます。
仕訳方法は以下のとおりです。
期首仕訳
|
借方 |
貸方 |
||
|
法人税等調整額 |
80,000円 |
短期繰延税金資産 |
30,000円 |
|
長期繰延税金資産 |
50,000円 |
||
期末仕訳
|
借方 |
貸方 |
||
|
短期繰延税金資産 |
30,000円 |
法人税等調整額 |
60,000円 |
|
長期繰延税金資産 |
30,000円 |
||
上記の例では、繰延税金資産の金額が前期より減っています。このような状態が「繰延税金資産の取り崩し」です。
下記の資料では、経理・財務部門で日常業務に活用している「Excel」に着目し、会計システムとExcelの併用がもたらす効率的な連携方法のポイントをまとめています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。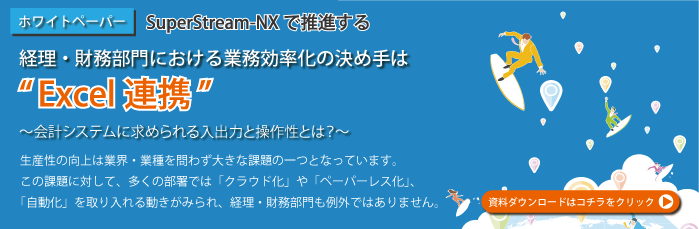
上記のように、繰延税金資産とは税効果会計において使用される勘定科目で、税金の前払い分にあたります。
企業会計と税務会計の認識の違いによって一時的な差異が生じた場合に、繰延税金資産を計上することで将来的な税負担の軽減につなげることができます。ただし、将来的にその差異が解消されることなどの条件があり、もし将来業績が悪化した場合は、いったん計上した繰延税金資産を取り崩して損失処理をしなければなりません。
回収可能性とは「繰延税金資産を将来的に回収できるかどうか」という可能性のことです。繰延税金資産は「税金の前払い」ですから、将来的に会計と税務の差異が解消されることが計上の要件となります。
将来的に繰延税金資産を回収できるだけの課税所得が見込めなければ、たとえ会計と税務の差異が発生しても、繰延税金資産を計上することはできません。そのため、繰延税金資産を計上する際には、その回収可能性について十分検討する必要があります。
下記の資料では、決算早期化を実施すべきためには財務経理部門が行うべきポイントを押さえつつ、「SuperStream-NX」を活用した解決方法を具体的に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。
繰延税金資産の回収可能性が失われるケースとは、将来的に会計と税務の差異が解消される見込みがなくなった場合です。
具体的には、将来減算する課税所得が見込めなくなった場合や、法人自体が存続できなくなるケースなどが該当します。このような場合には、繰延税金資産を取り崩して損失処理を行う必要があります。
下記の資料では、累計10,345社以上が導入し、高度な技術力で快適な操作性を提供している経営基盤ソリューション(財務会計|人事給与)SuperStream-NXの製品資料を無料でダウンロードできます。ぜひご参照ください。
上記のように、税効果会計による繰延税金資産の管理が必要となる対象は、主に上場企業や金融商品取引法の適用を受けている非上場企業、そして会社法上の大企業です。
繰延税金資産を管理する際は、複雑な計算や仕訳が必要となるため、クラウド会計システムを導入して効率よく管理するのがおすすめです。
クラウド会計システムで繰延税金資産を管理することで、繰延税金資産の計算や仕訳だけでなく、さまざまな業務の効率化も可能となります。
そこでおすすめしたいのが、キヤノンITソリューションズの「SuperStream-NX」です。
「SuperStream-NX」は、クラウド会計システムとして多くの企業に選ばれています。
高度な機能と操作性を備え、コスト削減や保守・管理業務の負担軽減が可能です。さらに、高いセキュリティと可用性を提供し、ビジネスの成長に応じた柔軟な拡張性も魅力です。
AI-OCRを活用した業務の自動化と効率化も実現しており、手作業によるミスを減少させ、業務効率を大幅に向上させることが可能です。
これらの理由から、「SuperStream-NX」は非常に優れた選択肢となります。
下記の資料では、「経営基盤ソリューション SuperStream-NX」の詳しい内容を解説しています。登録なしでご覧いただけますので、この機会にぜひご参照ください。
まずはオンラインでお気軽に資料請求してみてください。
また、自社に必要なシステムの種類や選び方がわからない場合は、いつでもキヤノンITソリューションズにご相談ください。貴社に適したソリューションを提供いたします。
国内1万社以上が導入する「SuperStream-NX」。下記の動画では、クラウド活用、システム連携、法改正対応の3つのポイントを解説しています。ぜひご視聴ください。